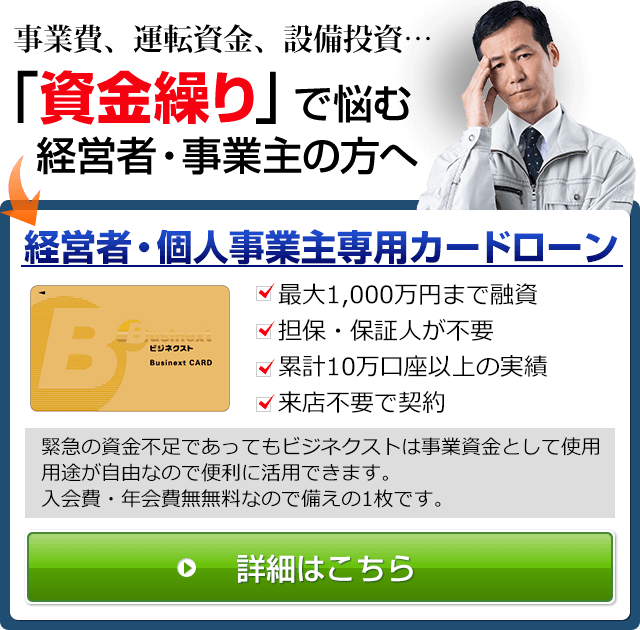青色申告と白色申告の違いとは

個人事業主として自営業やフリーランスとして働かれている方も年に一度、確定申告を行う必要があります。
確定申告とは、1/1~12/31までの期間に得た事業所得額を税務署に申告することで納税すべき所得税額を確定させることです。
申告する事業所得とは、売上金から経費や各種控除を差し引いた所得額になります。
つまり、経費計上や控除を多く受けることで納税対象となる事業所得を抑えることができ、結果的に納税額を節税することに繋がります。
個人事業主が所得申告をする場合は白色申告か青色申告を行うことになります。
何も届け出をしなければ白色申告になりますが、特別控除や税制上の特典がある青色申告をするためには一定の条件を満たす必要があります。
弥生株式会社の平成21年度のアンケート調査結果では、年収300万円以下で青色申告者は54%、年収が上がるにつれて青色申告者の比率は高くなり、1,000万円超では77%となっています。
しかし、それでも一定の割合の白色申告者が存在しているのが現状です。
今回は白色申告と青色申告の違いやメリット・デメリットから、なぜ白色申告者が一定の割合で存在しているのかまで解説していきます。
白色申告と青色申告の違い
控除を受けられるかどうかが白色申告か青色申告を選ぶ上で大きな判断要素となっています。
白色申告 |
青色申告 |
||
|---|---|---|---|
承認手続き |
なし |
所得税の青色申告承認申請書 |
|
特別控除 |
なし |
10万円 |
65万円 |
帳簿付け |
単式簿記 ※2014年より記帳義務化 |
単式簿記 |
複式簿記 |
決算書 |
収支内訳書 |
「損益計算書」 「貸借対照表」 |
|
赤字繰越 |
なし |
3年繰越が可能 |
|
専従者控除 |
配偶者86万円まで その他50万円まで |
制限なし |
|
元々は白色申告では帳簿付けの必要がなかったため、会計・経理処理にあまり時間を取れない方や開業してまもなく、事業所得が大きくない人が白色申告をおすすめしていました。

しかし、2014年からは白色申告でも帳簿付けが義務化され、領収書・請求書なども5年~7年は保管しておかなければならないようになるなど、白色申告でも手間が増えることになり、青色申告(単式簿記)との差は小さくなりました。
支払う税金は少しでも節税できるに越したことはなく、どうせ単式簿記で帳簿をつけるのであれば青色申告にして10万円の控除を受ける方が得だと考えられますね。
青色申告をすることができるのは、不動産所得、事業所得、山林所得のある事業者が対象であり、控除の有無以外にも白色申告にはないメリットが青色申告には多数用意されています。
白色申告のメリット・デメリット
個人事業主が所得税を確定させるための申告方法として最も手軽な方法は白色申告です。
青色申告にメリットが大きくても白色申告者が一定数存在しているのにはそれなりのメリットがありそうです。
白色申告は面倒な手続きがない
青色申告をするには届け出や複雑な帳簿付けが必要ですが、白色申告は事前の届け出は不要で帳簿付けも簡単です。
以前は帳簿付けさえ不要でしたが、現在は簡易簿記による帳簿付けが義務付けられています。
しかし、青色申告で大きな特別控除を受ける場合に必要な、複式簿記での帳簿付は必要ありません。
白色申告最大のメリットはこの手軽さにあります。つまり小規模の事業で、それほど大きな特別控除がなくても困らない事業者は申告の簡単な白色申告で十分だと考えているのです。

帳簿記帳方法は複式簿記と簡易簿記(単式簿記)の2種類があり、本来は正式な簿記に基づいた複式簿記で記入するのが正しいやり方です。
単式簿記では家計簿のように使った金額と残高がわかるように記述なので、誰でも記述しやすいというメリットがあります。
しかしこの方式だとお金を借りても収入扱いになるので、残高が多くても実は借金で成り立っている場合もあります。
複式簿記では借り方と貸し方に分けて記載するので、借金も考慮した結果、資産がどれくらいあるかということが明確になります。
しかし初めて帳簿をつけるときには、いきなり複式簿記で記載するのは難しいので、最初は白色申告から始めるというのが順当なやり方です。
白色申告の税制上のメリット

白色申告では税制上のメリットは、ほとんどありませんが「専従者控除」は認められています。
家族が申告者と同じ事業に年間6ヶ月以上従事していればその給与の一部が控除されるというものです。
控除された金額は税金の対象とならないので節税になります。ただし次のような条件があります。
- 対象者は生計を共にする親族であること(配偶者、子供、親など)
- 申告する年度の12月31日付で満15歳以上
- 年間で6ヶ月以上白色申告者の事業に従事している
- 配偶者の場合は86万円、その他の場合は一人につき50万円が控除の限度
- 専従者控除前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額が4より少なければ、これを控除金額にする
配偶者を含む専従者が3人いて、専従者控除前の課税所得300万円の場合、
4の控除金額86万円+50万円×2=186万円
5の計算による金額300万円÷4=296万円
この場合は4の控除金額186万円が適用になります。
白色の申告のデメリットを考えると、青色申告で受けられる税制上のメリットがないということになります。
同じ専従者控除でも青色申告では上限がありません。それでは青色申告にはどのようなメリットがあるのかご紹介しましょう。
青色申告のメリット・デメリット
青色申告では白色申告にはない税制上のメリット(各種所得控除)がたくさんあります。
これは簡易簿記ではわからない資産などが明確になる複式簿記で帳簿をつけていることも一つの理由です。
青色申告でも簡易簿記は認められていますが、特別控除の金額は極端に少なくなり、メリットはあまりありません。
青色申告にするのであれば複式簿記で帳簿付けをしましょう。
青色申告のメリット
- 複式簿記での帳簿付けをしていれば65万円、簡易簿記の場合は10万円が特別控除として認められる
- 赤字を3年間繰り越すことができる
- 事業専従者給与が全額経費として認められる
- 30万円未満の減価償却費は一括で経費計上できる
- 自宅兼オフィスの場合、光熱費・家賃など按分して経費にできる(家事按分)
2の赤字の繰越は、赤字が3年続いて黒字になった場合でも過去の赤字を差し引くことができるので、黒字の年度も税金がかからなくなる可能性があります。
控除が受けられるということはそれだけの収益を上げていなければなりません。
単純に事業所得での収入が50万円なのに控除額65万円を受けられたとしてもメリットは少ないと言えます。
しかし、青色申告なら事業が軌道にのるまで赤字を最大3年間繰り越せるのは大きなメリットです。
1年目・・・200万円赤字
2年目・・・100万円赤字
3年目・・・400万円黒字
400万円-(200万+100万)=100万円
2年目まで続いた赤字も、3年目の利益から差し引くことが可能となり、3年目の課税所得金額が節税できます。

3の専従者給与は白色申告と同じ条件ですが、控除額の上限がないので大きな節税につながります。
ただし、専従者になると配偶者控除や扶養控除も認められなくなるので注意しましょう。
白色申告では10万円以上の事業用の設備、機器の購入は資産として計上しなければいけません。
その場合耐用年数に応じて毎年少しずつ減価償却をして経費計上することになります。青色申告では30万円未満は一括で計上できるので経費がより大きくなり節税につながります。
自宅兼オフィスでは光熱費や家賃は個人の生活利用と事業利用が同時に請求されています。青色申告では説明できる根拠があれば比例按分して経費として計上ができます。
家賃であれば床面積の割合や、電気量であれば事業で使用するコンセントの数などの根拠が必要です。
家族の給与を経費にする
節税には経費をどれだけ上乗せするかが大きなポイントになりますが、青色申告であれば人件費を経費計上することができます。
白色申告では配偶者で最高86万、親族1人あたりでは50万円までを必要経費として計上できます。
しかし、青色申告では、配偶者や親族が従事可能な期間の1/2を超える期間を事業に関わることで労務に対する給与を必要経費として計上することができます。
貸倒引当金の計上

商売をしていると取引先との商品と金銭のやり取りには時差が発生することがあります。
商品を納品したけど、入金確認がまだなどの売掛金のことです。
先方の会社が倒産などの事情で売掛金が回収不能になったなどのに備えて、「貸倒引当金」として事前に経費として計上することができます。
これらのように青色申告では白色申告に比べて大きな節税効果があります。
白色申告では特に手続きは不要ですが、青色申告の場合、開業後2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければなりませんので注意してください。
青色申告のデメリット
青色申告をしてからのデメリットはありませんが、申告する前の手続きがあるという点がデメリットと言えます。
また、帳簿の記帳が複雑な点もデメリットの一つです。
■青色申告に必要な手続き
青色申告にする前には「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」と「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
これらの書類を提出していないと自動的に白色申告の扱いとなります。
開業届は開業から2ヶ月以内となっていますが、白色申告から青色申告に切り替えるときに、実際の開業日を記載して届け出をすれば問題ありません。
また、青色申告の申請書は青色申告をする年度の3月15日が締め切りです。これをすぎると次年度からになるので気をつけましょう。
■複式簿記での記帳
白色申告では確定申告で収支内訳書を記載して提出しますが、青色申告ではさらに「損益計算書」「賃借対照表」の提出が必要です。
こうした提出書類の多さが青色申告への切り替えを妨げる原因の一つとなって、白色申告者がなかなか減らない理由にもなっています。
しかし、申告書の作成ソフト、会計ソフトなどを利用すれば、これらは比較的簡単に作成することができます。
手続きが面倒という理由で青色申告をしていない人は一度検討してみると良いでしょう。青色申告にはそれだけのメリットがあります。
個人事業主の確定申告と経費

個人事業者の事業年度(決算期)は法人とは違い、一律に1/1~12/31までと決められています。給与所得者と違って必要経費も認められているので、申告する場合はなるべく経費を多く計上することで、支払う税金を少なくすることができます。
つまり経費に関する知識は個人事業主にとっては必要不可欠と言えるでしょう。ここでは確定申告で認められている各種経費を簡単に解説しましょう。
経費は勘定科目で覚える
会計ソフトを使えば経費の科目をすべて覚えていなくても選択することで記帳できます。
しかしある程度の知識がなければ選択することもできないのでよく使う経費科目は何を購入したときに使うのかは覚えておきましょう。
ほとんどの経費科目は名称だけで何に適用されるかは、わかるようになっています。
紛らわしい場合でも同じものを買ってその都度違う科目にせず、必ず同じものは同じ科目にするようにしていればそれほど問題は生じません。
■特別経費
給料賃金 外注工賃 減価償却費 繰延資産の償却費 貸倒金 地代家賃 利子割引料 固定資産等の損失
■その他の経費
租税公課 荷造運賃 水道光熱費 旅費交通費 通信費 公告宣伝費 接待交際費 損害保険料 修繕費 消耗品費 福利厚生費 雑費 専従者給与
これらの経費は年度中に計上することができ課税対象が隣りますが、高額な事業用の機器や設備を購入すると、経費として処理できる場合と、資産として計上しなければいけないケースに分かれます。その違いはどこにあるでしょうか。
経費と資産の違い
白色申告では10万円以上、青色申告では30万円以上で購入した備品や設備は固定資産として扱われます。
その為一度に経費処理できないので、耐用年数に応じた期間で減価償却費として経費計上します。
ただし、土地のように毎年価値が下がるものでない場合は減価償却の対象とはなりません。
■減価償却の計算方式
・定率法・・・償却費の額は初めの年ほど多く、年々減少する。
・定額法・・・償却費の額が原則として毎年同額となる。
■耐用年数
あらゆる動産に法律で決められた耐用年数が存在していて、小型自動車・パソコンは4年、牛や馬まで6年と定められています。
ちなみに、みかんの木は28年という長期の耐用年数です。減価償却費はこの年数の間計上することができます。
こうした資産には面倒な計算が伴うので、資産にしなくてもいい場合はリースを利用して賃貸借することをおすすめします。
リースにすればリース会社が固定資産税も負担し、リース料を経費計上すればいいので処理が楽になります。
まとめ
白色申告は基本的に事業規模が小さくそれほど節税効果が期待できない場合に行うといいでしょう。
サラリーマンや主婦の副業程度の事業規模の方におすすめです。それ以外の場合は青色申告を利用すると、はるかに節税効果が高くなります。
また初めて事業を行うという個人事業者は最初白色申告で慣れてから、次年度に青色申告に切り替えるという方法もおすすめです。
会計年度の途中から開業するのであれば、売上も少なく節税効果も見込めないからです。
いずれにしても会計ソフトなどを利用し、さらに自分でも簿記の知識を身につけるといった努力をすれば青色申告でもそれほど難しくはありません。
これから事業を始めようとする人には特に青色申告をおすすめします。