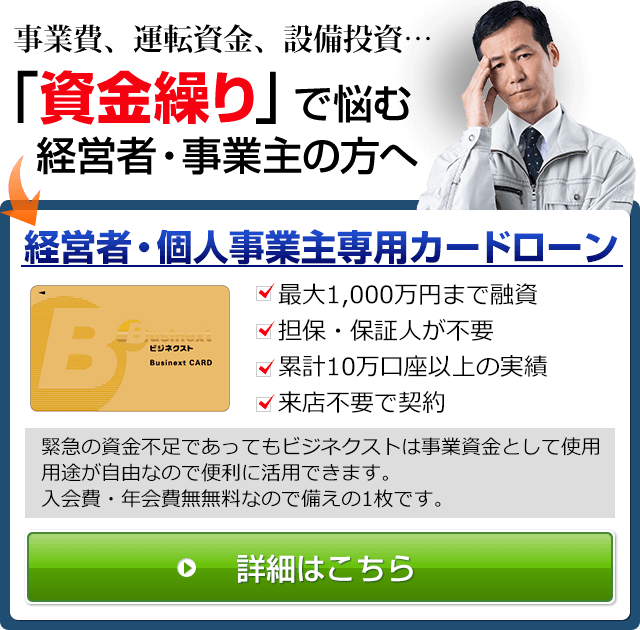所得税と住民税の違いと計算方法

所得税も住民税も所得によって税額が変わる税金ですが、異なる点も数多くあります。
会社員といった給与所得者の場合は、どちらも給与から天引きされるのであまり意識したことはないかもしれません。
しかしサラリーマンでもこれらの税金負担を軽減できる可能性があります。
また、個人事業主は確定申告によって所得税も住民税も税額が確定するので、税額がいくらになるのかを事前に知っておくことも大切です。
今回は所得税と住民税の違いやその計算方法について解説します。
所得税と住民税の違い
所得税も住民税も所得金額によって納税額が大きく変わる税金ですが、まずは所得税と住民税の違いから解説しましょう。
所得税と住民税の申告方法
所得税は国に収める税金なので国税のひとつですが、住民税は都道府県や市区町村に納めるので地方税という違いがあります。
どちらも納めた税金は行政サービスや福祉などに使われるので、国民や住民に還元されています。
申告については給与所得者と個人事業主によって違いがあります。
所得税の申告

給与所得者は源泉徴収による納税となるので、毎月の給与から天引きされます。
そのため個人で申告する必要はなく勤務先の企業が、給与計算の一環として社会保険料の控除や扶養者の人数を考慮して納税額を計算して給与から差し引きます。
個人事業主は毎年3月15日までに前年度の収入や経費の内容を申告し、各種控除を差し引いて所得を確定して納税額を申告します。
また個人事業主でも弁護士や司法書士の報酬、原稿料デザイン料などは源泉徴収税の対象となります。
これらの源泉徴収税は報酬の支払先が納付するので、確定申告では源泉徴収の税額を差し引いて申告することになります。
住民税の申告
住民税は地方自治体に納付するので、国税の所得税とは別に申告する必要があるはずですが、確定申告や年末調整をしていれば住民税の申告はしなくても構いません。
税務署が申告を代行する仕組みとなっているので、個人や企業が申告する必要がないからです。
確定申告が不要な人でも住民税の申告が必要な場合としては以下のケースがあります。
・20万円以下の給与所得以外の所得がある
・年金受給者の確定申告不要制度を利用した公的年金受給者のうち、年金以外の所得があった人
・退職などで年末調整をしていない給与所得者
・課税・非課税証明が必要となる場合(公営住宅入居者など)
納付方法の違い
所得税と住民税では納付方法も異なってきます。ひとつずつ解説していきます。
所得税の納付方法

所得税の納付は給与所得者の場合、毎月給与天引きされるため個人で納付する必要はありません。
支払い過ぎた税金に関しては年末調整によって還付することができます。
また、住宅ローン控除などの特殊な控除がある場合は、確定申告をして所得税の還付を受けることになります。
従業員の源泉徴収税を預かった会社は、給料日の翌月10日までに源泉徴収税を納付します。
ただし、納期の特例の承認を受けていれば、年2回下記の納期までに納付することができます。
1~6月分:7月10日まで
6~12月分:翌年1月20日まで
なお特例が適用される要件は「給与を支給する従業員が、常時9人以下であること」となります。
個人事業主は毎年確定申告日(3/15)までに全額納付するのが原則ですが、口座振替を選択した場合は4/20となります。
ただし確定申告書で延納の申請をすれば、半分以下の金額を5/31まで納付を伸ばすことができます。
延納には利子税(年1.8%)がかかりますが、1,000円未満は全額切り捨てのため、金額によっては利子税がかかりません。
住民税の納付方法

住民税の納付方法には「特別徴収」と「普通徴収」があります。
特別徴収は給与所得者が給与天引きによって納付する方法です。
普通徴収は自治体から送付される納税通知書と納付書によって納付する方法です。
給与所得者で給与以外の収入が一定以上ある場合は、確定申告をしますがその確定申告書で住民税の納付方法を選択することができます。
つまり給与所得者でも普通徴収で納付できる場合もあります。
納付の時期と納付方法は以下の通りです。
・毎年6/末の一括納付
・毎年6/末、8/末、10/末、翌年1/末の4期分割
一括と分割のどちらを選ぶかは、送付される一括の納付書と分割の納付書のどちらを使うかで決まるので、事前に分割の申請は不要です。
所得税はゼロでも住民税がかかる
所得税も住民税も所得を基準として課税される税金ですが、控除となる金額が違うため所得税では課税されなくても住民税では課税されるということがあります。
また、住民税には所得割と均等割がある点も所得税と大きく異なる点のひとつです。
所得割
所得割は所得金額に応じて課税される税金です。
課税所得金額が35万円を超える場合、所得割による住民税が発生します。
35万円を超える所得がある場合は、住民税の基礎控除33万円を控除することができます。
所得税の基礎控除は38万円なので、この差額によって所得税の課税がなくても住民税で課税されるケースもあります。
均等割
均等割は所得の金額に関係なく課税対象者に一律にかかる税金です。
課税対象者は自治体によって定められた一定の所得があり、1/1時点で市区町村に住所がある人となります。
また、均等割の場合は住所がなくても、事務所や家屋敷があれば課税対象となります。
住民税の納税義務がないケース
住民税の対象外
a.生活保護を受けている
b.障害者、未成年者(20歳未満)、寡婦または寡夫で前年の所得が125万円以下
c.合計所得金額が、市区町村の定める金額以下
所得割の課税対象外
a.控除対象となる配偶者・不要親族がいない場合、年間所得額35万円以下
b.合計所得金額が(控除対象配偶者+扶養親族+1)×350,000円+320,000円以下
均等割の課税対象外
合計所得金額が、市区町村の定める金額以下
所得割の基礎控除金額33万円は全国一律ですが、課税対象外となる基準の所得額は市区町村によって異なるので、自分の居住地域の金額を確認しておきましょう。
所得税と住民税の控除
所得税も住民税も所得金額から各種控除を差し引いた金額が課税対象所得となります。
控除の対象となる項目はほとんど共通していますが、控除金額が違う場合があるので比較表で確認してみましょう。
所得税と住民税で違いがある控除一覧
| 控除の種類 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 生命保険料控除 | 最高12万円 | 最高7万円 |
| 地震保険料控除 | 最高5万円 | 最高2.5万円 |
| 寄付金控除 | あり | なし |
| 障害者控除 | 27万円 | 26万円 |
| 特別障害者控除 | 40万円 | 30万円 |
| 同居特別障害者控除 | 35万円 | 23万円 |
| 寡婦(寡夫)控除 | 27万円 | 26万円 |
| 勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 |
| 扶養控除 | 38万円 | 45万円 |
| 特定扶養控除 | 48万円 | 38万円 |
| 老人扶養控除 | 63万円 | 26万円 |
| 配偶者控除 | 38万円 | 33万円 |
| 配偶者特別控除 | 最高38万円 | 最高33万円 |
| 基礎控除 | 最高38万円 | 最高33万円 |
所得税と住民税で同じ控除一覧
| 控除の種類 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 雑損控除 | 損失額に応じて控除 | |
| 医療費控除 | 医療費用から保険金を差し引いた金額が10万円を超える金額 | |
| 社会保険料控除 | 国民健康保険料、介護保険料など全額 | |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 全額 | |
| 青色申告特別控除 | 10万円または65万円 | |
所得税と住民税の計算方法
所得税と住民税の違いはその計算方法にもあります。
給与所得者の場合は計算する必要はありませんが、個人事業主は計算方法を覚えておくと、納付税額を事前に準備することができます。
所得税の計算
個人事業主の所得税の計算式は下記のとおりです。
{(収入-経費)- 所得控除 }×税率 - 税額控除
所得控除は基礎控除のように所得から差し引かれる控除ですが、税額控除は税率をかけた後で差し引きます。
税額控除には配当控除や外国税額控除、住宅借入金等特別控除があります。
また税率は所得金額によって税率と控除額が決められているので、国税庁のホームページなどで確認しておきましょう。
参考:所得税の税率(国税庁HP)
それでは具体的に所得控除後の金額が300万円で税額控除がない場合の計算をしてみましょう(税率10%:控除97,500円)。
平成49年までは復興特別所得税が加算されるので、所得税額の2.1%も納付します。
税率10%の場合は(10%×2.1%+10%=10.21%)として計算することで、合計の税額を同時に計算することができます。
300万円×10.21%-97,500円=208,800円(所得税額)
税額控除があれば上記の金額から差し引いた金額が納税額となります。
所得税の計算方法については、「所得税の計算方法とは?アルバイトやボーナスの扱いを解説」でも詳しく解説しているので参考にしてみてください。
住民税の計算
住民税には所得割と均等割がありますが、所得額に関係なく一律に課税される均等割額は計算の必要はありません。
都道府県民税は2,000円、市区町村民税は3,500円が標準となっています。
しかし居住地域によっていくらか違いがあるので確認しておきましょう。
所得割の計算方法
所得金額から各種の控除額を差し引いた金額に、都道府県民税は4%、市区町村民税は6%をかけることで算出できます。
しかし所得税と控除額の違いがあるので、平成19年から差額を調整するために「調整控除額」を最後に差し引きます。
住民税額=市区町村民税+都道府県民税-調整控除額
調整控除額は所得金額によって次のように計算します。
課税所得200万円以下
1.所得税と住民税の人的控除額の差額合計
2.課税される金額
上記の内、小さい額の5%
課税所得200万円超
1.所得税と住民税の人的控除額の差額合計
2.課税される金額-200万円
調整控除額=(1-2)×5% (2,500円未満には2,500円)
課税所得が200万円の場合の住民税を計算してみましょう(人的控除額の差額合計30万円)。
200万円×10%-(30万円×5%)=185,000円
均等割額の5,500円を加えた190,500円が住民税総額となります。
「所得税と住民税の人的控除額の差額合計」は、配偶者控除や扶養控除等の人的控除すべての差額を合計した金額のこと。
たとえば所得税では基礎控除額38万円となるが、住民税では33万円となるのでその差額は5万円となる。
まとめ
所得税と住民税の違いについてはおわかりいただけたでしょうか?
控除金額から計算方法まで違いがありますが、給与収入の場合はほとんど気にする必要はありません。
しかし個人事業主にとっては、控除を増やすことで所得税だけでなく住民税の節税も可能となります。
控除については常に最新情報を取得するよう心がけましょう。