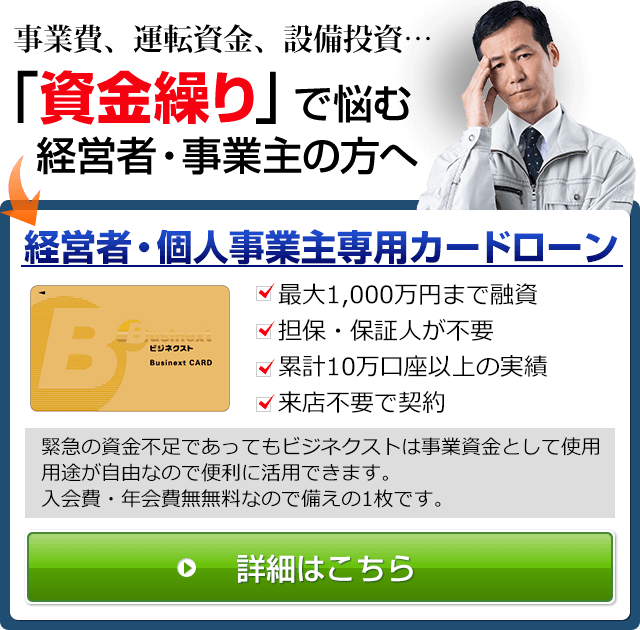所得税と住民税の違いと計算方法

納税は国民の3大義務のひとつなので、所得があればだれでも所得税を納める義務があります。
国に収める国税としての所得税の税率は基本的に職種を問わず一律ですが、年収の違いや給与所得か事業所得かによって控除など制度上の違いがあります。
また、同じサラリーマンでも年収によっては給料からの天引きだけではなく、確定申告によって申告するといった違いもあり、ケースによって申告方法から税額までさまざまです。
今回は年収別に所得税はどのように違うのかを解説しましょう。
所得と年収の違い
所得税について解説する前に所得税の対象となる「所得金額」と「収入金額(年収)」の違いについて説明します。
所得税に関する紛らわしい用語として収入と所得があります。
所得税は所得に対して課税される税金であって、収入に対して課税されるのではないというのが基本です。
所得税={(収入-経費)- 所得控除」 }×税率-税額控除
上記が所得税の計算式ですが、所得は収入から必要経費や各種控除を差し引いた金額のことを言います。
そして所得税の対象となる所得を「課税所得」と呼んでいます。
所得税の計算式は会社員も個人事業主も同じですが、給与所得者は経費がほとんど認められていないので、「収入-控除額」と覚えてもいいでしょう。
給与収入から給与所得控除を差し引いた金額が課税所得となります。

また、個人事業主は事業の売上のために使った経費を差し引いた金額が基本的な所得となります。
その所得からさらに控除額を差し引いた金額が課税所得です。
なお、同じ控除でも税額控除に関しては、一度税額を計算してからさらに差し引かれる控除です。
またサラリーマンは給与収入から社会保険料や源泉徴収税が差し引かれるので、手取り金額が少なくなります。
そのため所得金額と手取り金額はほぼ同じと考えてもいいですが、確定申告が必要な控除もあるので所得と手取り額は実質的には違うと考えましょう。
所得税の税率
所得税は基本的に下記のように税率が定められています。
所得税率表(A表)
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円を超え 330万円以下 |
10% | 97,500円 |
| 330万円を超え 695万円以下 |
20% | 427,500円 |
| 695万円を超え 900万円以下 |
23% | 636,000円 |
| 900万円を超え 1,800万円以下 |
33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円を超え 4,000万円以下 |
40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
上記の表のように所得税の対象となる税額によって決められた控除額を差し引いて税額を決定します。
課税対象となる所得ではすでに各種の控除を差し引いていますが、税額計算後にさらに上記の控除を差し引いた金額が実際の納税額となります。
課税の仕組みと控除の種類
給与所得者の場合の所得は「給与収入-給与控除額」、個人事業主の場合は「収入-経費」が所得となります。
給与所得者の給与控除額は給与週によって控除額は下記のとおりとなります。
給与収入と給与控除額(平成年31年分まで)- B表
| 給与収入額 | 給与控除額(計算式) |
|---|---|
| 162.5万円まで | 65万円 |
| 162.5万円超~180万円以下 | 給与年収×40% |
| 180万円超~360万円以下 | 給与年収×30%+18万円 |
| 360万円超~660万円以下 | 給与年収×20%+54万円 |
| 660万円超~1,000万円以下 | 給与年収×10%+120万円 |
| 1,000万円超 | 220万円 |
給与所得者のケースで具体的に計算すると年収300万円であれば、下記の所得金額となります。
300万円×30%+18万円=108万円(給与控除額)
300万円-108万円=192万円
給与所得者は年末調整で上記の金額から各種控除を差し引いて、すでに毎月の給与から差し引かれている税額よりも納税額が少ない場合は還付されるという仕組みです。
個人事業主の場合は、「売上-経費」から、さらに各種控除を差し引いた金額が課税対象となり、年1回の確定申告によって納税額を申告して納付します。
いずれの場合も課税金額は所得から控除される金額によって左右されることになります。
それでは所得から差し引かれる控除にはどのようなものがあるでしょうか?
控除の種類
所得から差し引かれる控除には人的控除と物的控除があります。
| 控除の種類 | 控除額 | |
|---|---|---|
| 人的控除 | 基礎控除 | 一律38万円 |
| 配偶者控除 | 38万円または48万円(70歳以降) | |
| 配偶者特別控除 | 最大38万円 | |
| 扶養控除 | 最大63万円 | |
| 障害者控除 | 最大75万円 | |
| 寡婦(寡夫)控除 | 27万円または35万円 | |
| 勤労学生控除 | 一律27万円 | |
| 物的控除 | 社会保険料控除 | 全額(国民健康保険料など) |
| 生命保険料控除 | 最大12万円 | |
| 地震保険料控除 | 最大1万5千円 | |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 全額 | |
| 医療費控除 | 最大200万円 | |
| 雑損控除 | 計算で算出 | |
| 寄附金控除 | 寄付額-2千円 |
サラリーマンの場合は基本的に年末調整で控除を申告しますが、医療費控除、雑損控除、寄附金控除に関しては確定申告が必要です。
また、控除には納税額から差し引かれる以下の税額控除もあります。
税額控除(抜粋)
・配当控除
・外国税額控除
・政党等寄附金特別控除
・公益社団法人等寄附金特別控除
・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除
・認定NPO法人等寄附金特別控除
税額控除はサラリーマンでも確定申告をする必要があります。
ただし住宅借入金等特別控除の場合、初年度は確定申告しますが、次年度以降は年末調整で申告可能です。
立場別の所得税計算
それでは、いくつかケース別に具体的な所得税の計算方法を説明しましょう。
年収300万円のサラリーマン
給与所得者の税額は最初に課税対象となる所得を計算します。
300万円の給与収入ではB表から「給与年収×30%+18万円」の給与得控除額を差し引きます。
課税所得=300万円-(300万円×30%+18万円)=192万円
次に課税所得から各種控除を差し引きます。
基礎控除の38万円と、社会保険料(仮に40万円とします)は、だれでも控除されます。
それ以外にも控除できるものがあれば、同様に差し引いてからA表の税率をかけて、さらに課税所得に応じた金額を控除します。
(192万円-38万円-40万円)×10%-97,500=97,500円
以上の計算により納税額は97,500円となります。
毎月の給与天引きで支払った税額が上記の金額以上であれば、その差額は年末調整することで戻ってきます。
また、10万円を超える医療費や住宅ローンを利用した場合は、確定申告によりさらに税金が還付され最大の97,500円が戻れば納税金額は0円となります。
年収100万円のパートアルバイト
パートアルバイトも給与所得者なので所得税の計算はサラリーマンと同様で、以下の通りとなります。
{(100万円-65万円)-38万円(基礎控除額)-12万円(社会保険料)}×5%=0円
収入が少なければ基礎控除を差し引いた時点でマイナスとなり、税率をかけるまでもなく所得税は0円となります。
つまり給与控除額と基礎控除の合計103万円の年収が所得税のかかるボーダーラインとなります。
また、主婦(主夫)の場合は、配偶者の所得から配偶者控除も認められているので、次の点に考慮して負担増とならないよう考慮する必要があります。
- 所得が38万円(収入103万円)を超えると配偶者控除は認められない
- 配偶者特別控除は年収に応じて控除が段階的に下がり、収入141万円以上は控除ゼロとなる
年間収入103万円を超えると配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除を受けることができます。
ただし一律ではなく年収によって3万円~38万円の控除額となります。

そのため主婦(主夫)がパートタイマーとして働く場合は、配偶者特別控除を受けられる収入になるように配慮する必要があります。
配偶者控除や配偶者特別控除は29年度に税制改正されているので、30年度以降は収入が150万円以下であれば控除を受けられことになりました。
こうした控除は毎年の税制改正で変わることがあるので、常に最新情報を確認して計算しましょう。
所得500万円の個人事業主
個人事業主の収入は給与収入と違い、収入から経費を差し引いた金額が、給与所得者の所得金額(控除前)に該当します。
経費を差し引いた所得が500万円の個人事業主の所得税額を計算してみましょう。
基礎控除や人的控除、物的控除の合計額は100万円、青色申告特別控除額を65万円とします。
課税所得=500万円-100万円-65万円=335万円
所得税額=335万円×20%-427,500円=242,500円
青色申告者の場合は10万円または65万円の特別控除が認められます。
その違いは複式簿記で帳簿を付けるかどうかだけなので、会計ソフトなどを利用して複式簿記での帳簿付けをしましょう。
控除金額が55万円増えるというのは大きな節税になります。
まだ白色申告という場合は、まずは青色申告の届け出をしましょう。
年金受給者の所得税
年金収入は所得の種類では雑所得となるので基本的に所得税がかかります。
しかし、以下の年金額の場合、所得税は免除されます。
- 65歳未満で受給額108万円以下
- 65歳以上で受給額158万円以下
上記の受給額以上であれば所得税がかかりますが、所得税は受給金額から源泉徴収されるので、400万円以下であれば確定申告の必要はありません。
ただし年間20万円を超える雑所得以外の所得がある場合は確定申告が必要です。
また、申告の義務がなくても医療費など確定申告をしなければ控除されないため、確定申告をして所得税の還付を受ける必要があります。
源泉徴収が基本となるため所得税の計算は給与所得者とほとんど同じと考えておきましょう。
まとめ
所得税の計算はおわかりいただけたでしょうか?
会社員の場合は毎月給与天引きとなるので計算の必要性は感じないかもしれませんが、確定申告によって控除されるものに関しては知識を深めておきましょう。
自営業者も控除に関する知識は必須と言えます。
特に青色申告特別控除は帳簿をきちんと付けるだけで65万の控除となるので節税効果が高くなります。
控除に関しては申告漏れがあっても税務署は教えてくれないので、自分で申告する必要があります。
所得税の計算方法とともに各種控除の知識も身に付けましょう。