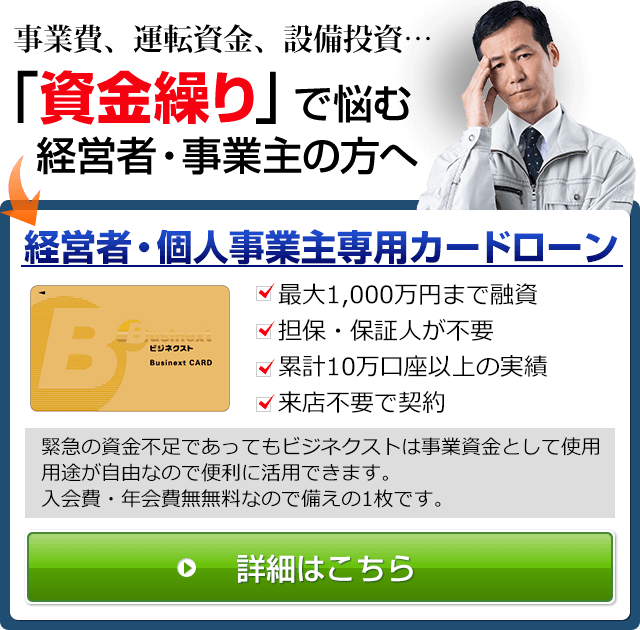銀行と信用金庫の違い

民間金融機関の代表的存在として銀行がありますが、同じ業務をしている信用金庫(信金)も存在しています。
銀行と信用金庫にはどのような違いがあるでしょうか?
事業者や経営者、消費者の立場で銀行と信用金庫のどちらを利用するとメリットがあるのでしょうか?
今回は銀行と信用金庫の違いについて解説しましょう。
銀行と信用金庫の基本的な違い
銀行と信用金庫はそもそも組織的にも法律的にも大きな違いがあります。
まずはその点から比較してみましょう。
組織と対象顧客の違い
銀行は株式会社という組織なので一般的な株式会社と同じように営利企業ということになり、株主に対する責任や法人として利益を求めるという基本的な理念があります。
一方で信用金庫は会員の共同出資による非営利法人です。
ちなみに信用組合も組合員の出資による非営利法人で、信用金庫と立場はほぼ同じです。
つまり銀行の目的は最終的には営利ですが、信用金庫は会員(信用金庫は組合員)の相互扶助が目的となります。
ただし銀行・信用金庫ともに国民や大衆の金融の円滑化を図るという共通目的も存在しています。
業務の対象となる範囲に大きな違いがあり、銀行は不特定多数、信用金庫は地域内の会員を対象としているのです。
具体的には次のような違いがあります。
| 銀行の対象顧客 | 制限なし |
|---|---|
| 信用金庫の対象顧客 |
地域内に住所地または住居や事業所を有する者(地域住民) |
上記の条件をみると信用金庫は事業者としては地元中小企業や店舗を取引先としていることがわかります。
つまり、信用組合や信用金庫は銀行と違って、協同組織や協同組合といった限定した範囲の中で営業活動をしているのです。
業務範囲の違い

銀行も信用金庫もほとんど同じ業務内容ですが、まったく同じではありません。
銀行は銀行法、信用金庫は信用金庫法によって規制が行われている、まったく違う組織となります。
しかし、預金や融資を行なうという点では同じですが、取扱対象者は信用金庫は銀行に比べて制限があります。
信用金庫が預金を受けたり融資できたりするのは会員に限られるという点です。
ただし、3年以上5年未満で脱会した場合は5年間、5年以上会員であった場合は、脱退後5年間は融資を受けられます。
これを卒業生金融と呼んでいます。
消滅時効の違い
消滅時効は最終返済から一定期間を経過すると、債権が消滅することをいいます。
まったく取り立てをしない債権者に長期間の権利を認めないという趣旨によるものです。
この一定期間は基本的に、債権者または債務者のどちらかが商人であるかどうかで、5年と10年に分けられます。
銀行は営利団体なので商人とみなされ消滅時効は5年となります。
同様に貸金業者(消費者金融会社・信販会社・クレジットカード会社等のノンバンク)も5年です。
信用金庫や信用組合、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)、信用保証協会等は商人とみなされないので、10年となります。
ただし、商人かどうか以外にも消滅時効が延長する要素があリます。
例えば、消滅時効が5年であっても強制執行などを受けると、その時点から時効消滅までの期間が10年となるので注意しましょう。
金融機関としての違い
銀行と信用金庫の根本的な違いがわかったところで、具体的に利用する上ではどのような違いがあるでしょうか?
銀行や信用金庫でも事業者融資やカードローン、住宅ローンといった金融商品を提供していますが、どちらを利用するとメリットが大きいでしょうか?
企業規模によって選ぶ

これまでの解説で大企業はそもそも信用金庫からは融資を受けることができないことがわかったと思います。
企業規模に制限があるのでその範囲内の中小企業しか融資は受けられません。
また、地元の資本で運営しているので、地元産業の活性化といった目的もあり、中小企業はまず信用金庫からの融資を目指すといいでしょう。
都市銀行や地方銀行よりは融資を受けやすいというメリットがあります。
しかし、会員の出資によってまかなっているため、高額な融資に対応できないというデメリットもあります。
最初は信用金庫の取り引きを中心にして、事業規模が拡大するにつれて銀行取引にシフトしていくといいでしょう。
しかし、最近では信用金庫も合併などにより、メガ信用金庫と呼ばれる信用金庫も存在しています。
規模が大きい信用金庫であれば、事業規模が拡大しても対応できるので、無理に銀行にシフトする必要はないでしょう。
融資審査に違いはあるか?

信用金庫の場合、営業地域が限定されていて事業融資の対象も地元の中小企業に限定されています。
必然的に書類上ではわからない情報も入手できるので、銀行のように決算書を中心とした審査ではなくなります。
融資額にも限度があることを含めて、銀行と比べると信用金庫の審査基準はそれほど厳しくないと判断できるでしょう。
これは消費者を対象とした個人向け融資やカードローンなどにもいえます。
地元に長く居住している人が対象となることが多いので、一般の融資でも比較的通りやすいというのは事実です。
ただし、審査基準が特別甘いわけではなく、過去に金融事故やクレジット事故があれば、審査を通過しないのは信用金庫でも同じです。
預金者としてはどちらにメリットがあるか?
預金利用者としては、銀行と信用金庫のどちらにメリットがあるでしょうか?
預金金利に関してははっきりいって銀行も信用金庫もほとんど同じといっていいでしょう。
信用金庫は地元に密着しているので企画商品などがある分、定期預金などはやや有利かもしれません。
しかし全体的に低金利の時代となっているので、金利を比較しても大きなメリットは得られません。
むしろ使いやすさで比較して選ぶといいでしょう。
全国に支店・ATMがあるメガバンクであれば、提携ATMを利用するときの手数料を節約できます。
地方に居住していても子供が都心部の大学に通っているのであれば、メガバンクが便利でしょう。
また引っ越しが多い転勤族も信用金庫よりはメガバンクのほうが便利です。
一方、地域社会内で金融機関を利用するのであれば、地元の信用金庫のATMを利用するほうが便利で手数料もかかりません。
このように使い方に応じて銀行か信用金庫かを選びましょう。
信用金庫の配当メリット

信用金庫には銀行にはない配当というメリットがあります。
まず信用金庫を利用するためには一般的に1万円程度の出資金を支払う必要があります。
この出資金は脱会したときに戻ってきますが、信用金庫が破綻したときには戻らない可能性もあります。
信用金庫は非営利団体なので利益は出資した会員に配当金という形で還元されます。
預金金利とは別に出資金に対して配当金があるというのは銀行にはない信用金庫のメリットです。
出資金が多いほど配当金も大きくなりますが、配当目的で会員となることはできないので、基本的には10万円を出資金の上限としています。
定期預金でも0.1%という時代なので、少なくてもそれ以上の配当が見込めるのは大きなメリットです。
就職先としての銀行と信用金庫
一般的には銀行のほうが大規模で就職先としては安定しているので有利と考えられます。
しかし、銀行と信用金庫では組織が違うのでその理念もまったく異なっています。
最終的には利益を追求する銀行に比べて、信用金庫は利益を地域会員に配当する非営利団体です。
この点を考慮すると地元に貢献したいと考えるのであれば、銀行よりも信用金庫を選択すべきということになります。
また、特にメガバンクに就職すれば全国に転勤する可能性があり、地元に戻ることはほとんどなくなります。
そうした点からも信用金庫を選択する意味はあるでしょう。
就職先を選択する基準はいろいろありますが、金融機関の就職を目指すのであれば、その組織の設立理念も考慮して選択しましょう。
まとめ
銀行と信用金庫の大きな違いは金融機関業務ではなく、その対象者が違うというのが結論です。
銀行と信用金庫、どちらも利用できる地元中小企業や地域住民にとっては、自分にメリットがある金融機関を選ぶことが必要です。
どちらか一つを選ぶということではなく、使い方によって金融機関を選択するということが大事です。
特に事業資金調達に利用するのであれば、その金額や審査の通りやすさを比較して利用しましょう。
都銀・地銀・信用金庫(信用組合)はそれぞれにメリットがあるので上手に使い分けることが大切です。