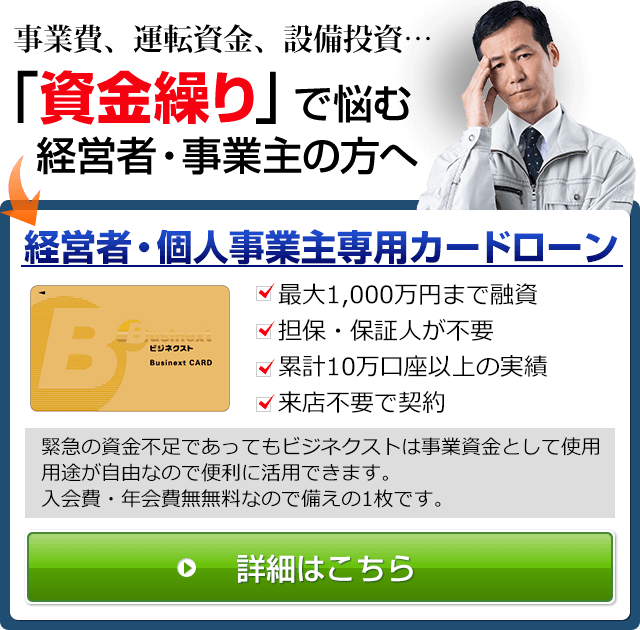所得税の計算方法とは?アルバイトやボーナスの扱いを解説

所得税は、一定以上の収入がある人であれば、個人事業主でも、会社員でも、アルバイトでも収めなければならなりません。
毎月所得税を給与から天引きされている方の場合、所得税について意識することは中々ないかもしれませんが、損をしないためにはその計算方法や還付の申告方法などについて知っておくことが大切です。
所得税の仕組み

所得に対する税金は、個人の場合は「所得税」、法人の場合は「法人税」として徴収されます。
法人税については「法人税の税率まとめと基礎知識」のページで解説しているので今回は割愛するとして、給与所得者や個人事業主を対象とした所得税の仕組みについて説明しておきましょう。
個人に対する所得税率は、あなたが個人事業主であるか給与所得者であるかに関わらず、年間の所得額が大きい人ほど高くなります。
これは、今日の日本が「累進課税制度」といって課税対象の金額(今回のケースでは所得額)にあわせて税率が上がっていくシステムを導入しているからです。
所得税の対象となる所得額は、額面の年収ではなく、基礎控除や配偶者控除などを差し引いた「課税所得」です。
あなたが会社員であれば、源泉徴収票には次の4つの金額が記載されていると思いますが、
1.給与収入金額
2.給与所得控除後の金額
3.所得控除の額の合計額
4.源泉徴収税額
課税所得は、このうち「2.給与所得控除後の金額」から「3.所得控除の額の合計額」を差し引いた金額となります。
この課税所得に税率を掛けた金額が「源泉徴収税額」です。
(2-3)× 税率=源泉徴収税額
源泉徴収税とは、会社の年間の給与から引かれる所得税のことです。
会社員の場合、おおくのケースで源泉徴収税がそのまま年間の所得税となりますが、Wワークによる収入が一定額を超えている場合にはそのほかの所得も合算し、別途確定申告を行って所得税額を確定させなければなりません。
個人事業主の場合は、源泉徴収をしないためみずから確定申告をして所得税額を確定させます。
所得税の税率
所得税の税率は下記の表のように課税所得額によって課税控除額とともに決められています。
課税所得金額 |
税率 |
課税控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超え330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超え695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超え900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超え1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超え | 45% | 4,796,000円 |
たとえば、課税所得が300万円の場合、所得税額の計算式は次のとおりです。
300万円×10%-97,500円=202,500円
なお、平成37年までは上記の所得税額に対して2.1%の復興特別所得税※が加算されるので、最終的な所得税は下記のとおりとなります。
※復興特別所得税・・・東日本大震災からの復興に向けて必要な財源を確保するために設けられた特別措置
202,500円×2.1%(4,252円)+202,500円=206,752円
税額は源泉徴収税額表にもとづいて決まる

正社員の源泉徴収税額表
給与所得者の場合、毎月の給与から差し引かれた源泉徴収税は「源泉徴収義務者」によって税務署に納付されます。
源泉徴収義務者とは、具体的にいえば会社や雇用主などの事業者です。
事業者は「源泉徴収税額表」に基づいて給料から税額を差し引いて預かり、給料支払日の翌月10日までに税務署に納付します。
納期の特例によりある条件を満たすと納付回数を年2回にすることもできますが、かねがね納付のタイミングは毎月10日です。
源泉徴収税額表は3種類あります。
月額給与の場合は「月額表」、日払いや週払いの場合は「日額表」、賞与(ボーナス)は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使用します。
下記画像のとおり、各表は甲欄と乙欄に分かれており、甲欄には給与所得者の扶養者人数におうじた税額が記載されています。
また、対象となる給与額は社会保険料を控除した金額となります。
パート・アルバイトの源泉徴収税額表

パート・アルバイトも基本的には月額表や日額表で源泉徴収額を計算するので、正社員と変わるところはほとんどありません。
ただし、雇用契約書で2ヶ月以内の期間を定めた場合や、日雇いで2ヶ月を超えて給与を支払わない場合は甲欄を使わずに乙欄で計算するという定めがあります。
しかし、主婦のパートは配偶者の扶養控除の対象となるので、源泉徴収された税金は本来納付義務がないことになります。
そのため、扶養控除の対象となる範囲の所得であれば、バイト先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出して年末調整をしてもらいましょう。
提出していない場合は自分で確定申告をする必要があるので、源泉徴収票を持って税務署に相談しましょう。
確定申告といっても還付のためだけの簡単な記載なので、その場で申告書を作成して提出できます。
所得税の還付
給与所得者でも個人事業主でも所得税は申告によって還付されることがあるので、申告方法はかならず覚えておきましょう。
給与所得者は年末調整で申告
源泉徴収の際には各種控除のうち一部の控除しか行われていません。
そのため、年末調整することによって払いすぎた税金を還付してもらえるのです。
| 人的控除 | 基礎控除や配偶者控除(配偶者特別控除)、扶養控除、特別障害者控除、勤労学生控除等、人に対する所得控除 |
|---|---|
| 物的控除 | 生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除などの所得控除 |
上記の所得控除を年末調整で申告しますが、医療費控除や住宅ローン控除など特殊な控除については、サラリーマンでもみずから確定申告しなければなりません。
なお、住宅ローン控除や寄付金控除は、所得控除ではなく、いったん所得税額を算出してから差し引かれる税額控除となっているので、節税効果が高くなります。
なお物的控除では社会保険料を除いて控除証明書が必要となるので注意しましょう。
個人事業主は確定申告が基本

個人事業主の事業年度(決算期)は1/1から12/31となっていて、事業年度終了後の翌年の3/15の申告期限までに確定申告書を提出して納税します。
前年の年税額が48万円を超えると中間申告が必要となり、年1回から最大11回の中間申告が義務付けられます。
提出期限に遅れるだけでペナルティがあるので注意しましょう。
また同じ個人事業主でも白色申告者と青色申告者では、青色申告特別控除など所得控除に大きな差があります。
現在白色申告の個人事業主は早めに青色申告に切り替えると大きな節税になります。
また、確定申告書では所得控除の申告もすべて行ったうえで所得税額を確定させるので、基本的には所得税の還付とは無関係と思われるかもしれません。
しかし、個人事業主でも源泉徴収される報酬があるので、源泉徴収の対象となる報酬がメインの場合は、確定申告によって税金が還付される可能性が高くなります。
また還付まではいかなくても源泉徴収の税額が相殺されるので、節税の効果があります。
個人事業主も源泉徴収された報酬額は忘れずに確定申告しましょう。
まとめ
税法は改正が多い法律で期間限定の特例なども数多くあります。
会社経営者はもちろんですが、個人事業主や給与所得者も税制改正の情報には注意する必要があります。
実際に所得税の控除については、配偶者控除という多くの人が関係する控除の改正も行われています。
税金は自分で申告しなければお金が戻ってくることも、優遇措置を受けることもできないので、サラリーマンでも税金に関する基礎知識は身につけておきましょう。