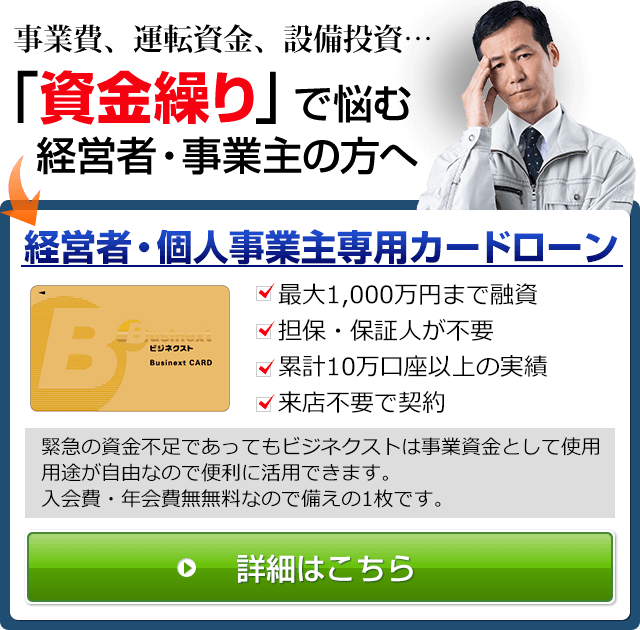個人事業主の赤字に備える青色申告書

個人事業主となると自分自身の売り上げ額がそのまま所得額となるので、事業継続させるためには、安定した売り上げをキープする必要があります。
また売り上げだけがあれば良いのではなく、あくまで利益としていくら手元にお金を残せているかが事業の重要ポイントです。
利益は、売り上げから必要経費(仕入れ額など)を差し引いたものです。
例え、月100万円を売り上げたとしても在庫キープのために仕入れや経費などで120万円かかってしまうと20万円の赤字になるのです。
ここでは個人事業主における赤字の扱いについて説明していきます。
個人事業主でも赤字は十分にあり得る

自分ひとりで事業をしている方も多くいらっしゃるかと思いますが、それでも事業をしていると赤字になるケースは十分にあり得ます。
季節や天候にも釣果の影響が左右される漁師を例にしますと、魚を獲れようが獲れまいが毎日のように海原に漁に出て行きます。
船のリース代やガソリン代などは関係なく発生します。
釣果が悪いと当然ながら売り上げ(漁師の収入)にもダイレクトに影響がでるので、必要な経費の方が多くなることもあるのです。
開業したての個人事業主であれば、事業収入が安定するまで会社員時代の貯金などを切り崩しながら生活をすることもあります。
もし、事業で利益を残せなかった場合、貯金を活用することによって生活上は問題ないかもしれませんが、確定申告書において事業は赤字の扱いとなります。
所得税の節税にもなる赤字
所得税は売り上げから必要な経費を全て差し引き、最終的に残った年間所得(利益額)に対してかかることから、あえて経費を積み上げて節税するケースもあります。
当然ながらギリギリまで経費計上することもありますが、売り上げ見込み以上に計上やりすぎたり、想定外な出費が加わると赤字になってしまうことも考えられます。
所得税額の税率として、所得額195万円以下であれば控除額は0円であり、もし、赤字決算であっても所得税は免除されることになります。
所得税には基礎控除がある
確定申告・年末調整などにおいて所得税を計算する際に、総所得金額から基礎控除として一律38万円の控除を受けることができます。
つまり、事業を始めたばかりで初年度の所得金額が38万円以下の場合には所得0円の扱いとなり、所得税が発生しません。
▼確定申告の条件
・給与所得がある方
・公的年金などにかかる雑所得のみの方
収入400万円以下、雑所得が20万円以下なら確定申告不要
・退職所得のある方
副業として20万円以下の収入を得ている方は確定申告をする必要はありませんが、事業を専業としてされており、基礎控除の38万円を超える所得がある場合には確定申告しておきましょう。
青色申告決算書による赤字の繰越
確定申告書は白色申告書と青色申告書のいずれかで行うことができますが、青色申告者であれば損失申告として最大で3年間の赤字繰越ができる特徴があります。
赤字であっても確定申告しておけば、黒字化した時に所得税の節税にも繋げられます。
1年目・・・50万円の赤字
2年目・・・20万円の赤字
3年目・・・100万円の黒字
この場合、1年目と2年目では所得税が発生していません。
これらを確定申告しなければ3年目の100万円に対して5%(50,000円)の所得税を支払う必要があります。

しかし、初年度から確定申告をしていると以下のように繰越ができます。
100万円(3年目)-70万円(1年目+2年目)=30万円
3年目に支払うのは30万円に対しての5%(18,000円)となるのでお得です。
最初から赤字に備えてというわけではありませんが、事業が軌道にのるまでは赤字になることも十分に考えられます。
白色申告者では10万円の控除しか受けられませんので、節税効果を高めるという意味でも最大65万円の青色申告特別控除を受けられる青色申告での確定申告をおすすめします。
個人事業主では消費税にも発生条件がある
個人事業主が支払う税金には以下のようなものがあります。
・所得税
・住民税
・個人事業税
・消費税
このなかでも消費税の扱いは特殊なのかもしれません。
まず提供するサービスや商品などの売り上げが課税所得となるのかどうかを確認する必要があります。
自分たちの売り上げとは関係なく、国に収める費用になるので、免除できるならしたいところではないでしょうか。
個人事業主の場合、最初の2年間は免税事業者として事業を行うことができます。
この免税か課税かの判断は、2年前の収入額を元に消費税の支払い有無が判断されることになるからです。
売上高1,000万円以下は免税事業者
消費税には免税事業者・課税事業者がありますが、開業から2年間は所得がないので免税事業者となるのです。
赤字に備えて共済への加入を検討
個人事業主は法人などに所属していないため、退職金や個人年金などを自分自身で対応していかなくてはなりません。
貯金など自分で積み立てがきちんと継続してできるのであれば問題ありませんが、あらかじめ共済制度などを活用するという方法もあります。
・小規模企業共済
・経営セーフティ共済
これらは経営者や個人事業主を守るための制度となります。
小規模企業共済は、積み上げてきた掛金に応じて退職金として受け取れる制度であり、経営セーフティ共済は中小企業を対象に取引先の影響から連鎖倒産などの危機に共済金としてサポートを受けられるものです。
個人事業主であっても、取引先が急遽倒産して収入が見込めなくなって急遽赤字になるということも十分考えられるのです。
まとめ

個人事業主は、給料だけでなく健康保険や税金対策も全て自身で考えなければなりません。
急に税務署による税務調査が入ってもキチンと対応できる体制を整えておきましょう。
税金関連のことに関しては個人事業主として事業を続けていくなら最低限の知識は身に付けておいたほうが控除などメリットをフル活用できます。
青色申告書では、専従者給与なども経費としてみなすことも可能なので、節税対策にお役立てください。