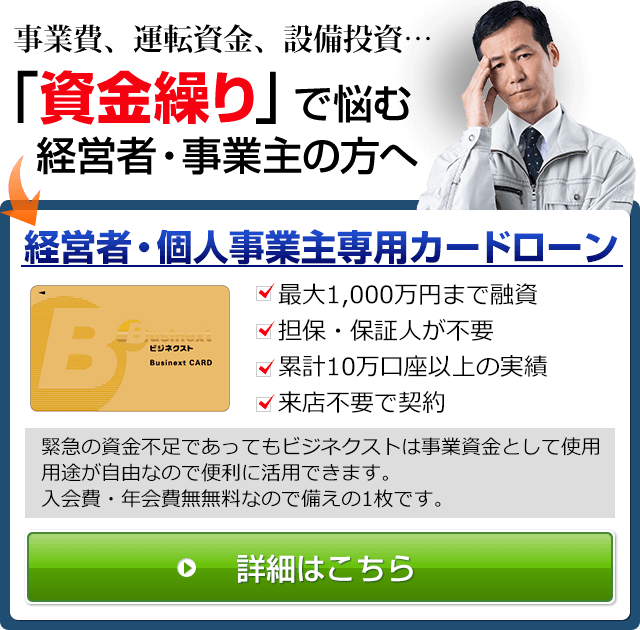住民税における所得割と均等割の違いとは?

住民税は地方自治体に納める地方税ですが、その仕組みについては詳しく知らない人も多いでしょう。
特に給与所得者は毎月の給与から天引きされているため、ほとんど意識することもないでしょう。
事業者でも所得税の申告はしますが、住民税は自動的に税務署が申告するので、送付される納付書通りに納めるだけという人がほとんどです。
しかし、住民税もその仕組みを理解することで節税することも可能です。
今回は住民税の仕組みや種類などを詳細に解説しましょう。
税法上の所得と会計上の利益の違い
住民税は、だれがどこに収める税金でしょうか?まずは住民税の対象者から解説しましょう。
住民税の対象者
住民税は1月1日時点で住民票がある人であれば、必ず納めなければいけない地方税です。
市町村税と都道府県税に分かれていますが、基本的に市町村に全額納付すれば、各市町村が住民に代わって道府県に納付します。
例外的に東京都だけは東京都に納付します。
市町村民税も東京都だけは「特別区民税」という名称ですが、納税の仕組みや内容は同じです。
住民税の納付義務がないのは以下のケースとなります。
・生活保護者
・年間所得125万円以下の障害者、未成年、寡婦
・市町村が定める金額以下の所得だった場合
後で詳細を解説しますが、住民税には「所得割」と「均等割」があります。
上記のケースではどちらの納付義務も免除されます。
所得割の納付義務だけがないケースは次のとおりです。
・控除対象配偶者と扶養家族の人数✕35万円+32万円以下の所得の場合
・所得が35万円以下の場合
上記のケースを除いて一定以上の所得がある人は、全員住民税の納付義務があることになります。
所得割と均等割の違い
住民税には「所得割」と「均等割」の2種類があります。
| 所得割 | 前年の所得金額に応じて納付する住民税 |
|---|---|
| 均等割 | 所得金額に関係なく一律に納付する住民税 |
所得割に関しては一定以上の所得がなければ納税義務はありませんが、均等割は一部の例外を除いて住民税の対象者は全員納付することになります。
住民税の税率は市区町村によって違いがありますが、基本的には次の税率となっています。
| 所得割 | 市町村民税6%+道府県民税4%=合計10% |
|---|---|
| 均等割 | 市町村民税3,000円+道府県民税1,000円=合計4,000円 ※復興増税は考慮しない |
所得割額は所得が大きいほど納付額も大きくなりますが、均等割額は一律の金額となることがわかるでしょう。
正確な納税額が知りたい場合は自分の市町村のホームページなどで確認しましょう。
それでは次に住民税の納付方法を解説しましょう。
住民税の納付方法と種類
住民税には2種類の納付方法があります。
・特別徴収
・普通徴収
サラリーマンといった給与所得者は住民税は直接納付せず、事業者が給与天引きで預かってからまとめて納付します。
これを特別徴収と呼んでいます。

それ以外は税務署から送付された納付書で支払いをする普通徴収となります。
事業主や年金受給者、退職したサラリーマンなどが普通徴収となりますが、確定申告をする必要がある給与所得者はどちらで納付するか選択することができます。
サラリーマンが副業として事業をしている場合は、特別徴収のまま住民税を支払うと、会社に副業が発覚することもあるので注意しましょう。
しかし、普通徴収に切り替えても会社に疑われる原因になるので、副業禁止の企業で副業をすること自体を避けたほうが無難です。
所得割・均等割以外の特殊な住民税
住民税は所得金額をベースとして課税されますが、所得の中でも次の所得では所得割・均等割以外の住民税を支払う必要があります。
| 利子割 | 利子所得の金額に応じて納める住民税 |
|---|---|
| 配当割 | 特定配当等の額に応じて納める住民税 |
| 株式等譲渡所得割額 | 場株式等の譲渡による所得に応じて納める住民税 |
事業所得や給与所得以外に上記の所得がある場合は住民税が加算されるので注意しましょう。
住民税の対象となる所得と控除
住民税は確定申告書に記載された内容がベースとなっているので、基本的に所得税の課税所得金額が対象となります。
住民税の所得控除
住民税の課税所得は所得金額から所得控除を差し引いた金額となります。
所得税の控除とほぼ同じで以下の所得控除があります。
・雑損控除
・医療費控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・障害者控除
・寡婦(寡夫)控除
・勤労学生控除
・配偶者(特別)控除
・扶養控除
・基礎控除(一律33万円)
・給与所得控除(給与所得者は一律65万円)
上記は所得税申告の場合の所得控除と同じですが、住民税には所得税の申告で認められている税額控除はありません。
つまり青色申告であっても住民税額から65万円が控除されません。
その代わり青色申告者の場合は所得控除として65万円の控除を受けることができます。
住民税の節税

住民税の所得控除は、所得税の所得控除に比べて金額が少なくなっている控除があるのにお気づきでしょうか?
所得税の基礎控除は38万円ですが、住民税の場合は33万円となっています。
そのため所得税の課税がなくても住民税の所得割が発生するというケースもあります。
住民税は所得税以上に節税を意識する必要があります。
とは言っても住民税の節税は所得控除を増やすしか方法がありません。
上記の所得控除を見直すとともに、白色申告者は青色申告に切り替えることを検討しましょう。
単純に住民税を10%と考えると、青色申告特別控除の65万円が差し引かれるだけで、年間65,000円の節税になります。
それ以外の所得控除は、実際に支払いが発生したり、意図的に操作できなかったりといった控除ばかりです。
支出もなく書類提出だけで節税可能な青色申告は、個人事業主にとって必須といえるでしょう。
住民税に関連する注意点
それでは最後に住民税に関連した注意点をまとめてみましょう。
サラリーマンが退職した場合
サラリーマンの場合は給与天引きの特別徴収によって住民税を納付しています。
退職することで給与収入がなくなるので、住民税を完納していない状態で退職した場合は次の手続きをします。
1.退職月の給与で一括天引き
2.転職の場合は新しい会社で給与天引き
3.普通徴収にして自分で納付する
上記いずれかの方法で退職後も住民税を納付することができます。
住民税を滞納した場合

サラリーマンは給与天引きなので延滞することはありません。
会社が納付していない場合は、会社に責任があるので会社に対して延滞金がかかることはあります。
しかし、個人事業主など普通徴収で納付している場合は、納期限を過ぎても支払わないと督促状などが発送され、延滞金も加算されます。
長期の延滞になると資産の差押となる可能性もあるので、早めに納付しましょう。
差押物件を換金しやすいという理由から、最近では差押えた物件をネットオークション等で処分して、住民税に充当する自治体も増えています。
こうした差押はむやみに行うわけではなく、悪質と判断した場合に限られます。
納付が難しいとわかった時点で、市町村の窓口で相談しましょう。
支払う意思を示すことで差押といった強制手段を回避することができます。
引っ越しした場合
住民税は1月1日時点の住所地の市町村が住民に課税する税金です。
そのため引っ越ししても完納するまでは以前の住所地の自治体に納付することになります。
特に変更手続きは必要ありませんが、住民基本台帳法に基づいて転出・転入届けをする必要があります。
転出・転入届けをしないまま引っ越しをすると、法律で最大5万円の科料が科せられることがあります。
住民税への対応に限らず、住民票の異動は生活する上での基本となるので忘れないようにしましょう。
アルバイトの住民税
アルバイトも給与所得なので雇用主に給与天引きの義務があります。
しかし実際はパート・アルバイトについては、住民税の給与天引きをしていない雇用主が多いのが現状です。
給与所得控除と基礎控除の合計金額を超える所得の場合は、アルバイトでも住民税の所得割の対象となるので注意しましょう。
もちろん基本的に均等割の納税義務もあります。
給与天引きされていない場合は、所得金額が年間100万円以上であれば、所得割の納付書も届くと考えておきましょう。
まとめ
住民税の所得割と均等割についておわかりいただけたでしょうか?
基本的には行政サービスを受けるために必要な税金なので、所得がなくても納付義務があります。
所得税は2分割しかできませんが、住民税は4分割と一括払いの選択ができるので支払いやすくなっています。
きちんと支払うために事前にシミュレーションなどでどれくらいの課税となるのかを調べておきましょう。
もし納付が難しい場合でも市町村に相談すれば、さらに分割払いも可能なので放置することだけはやめましょう。