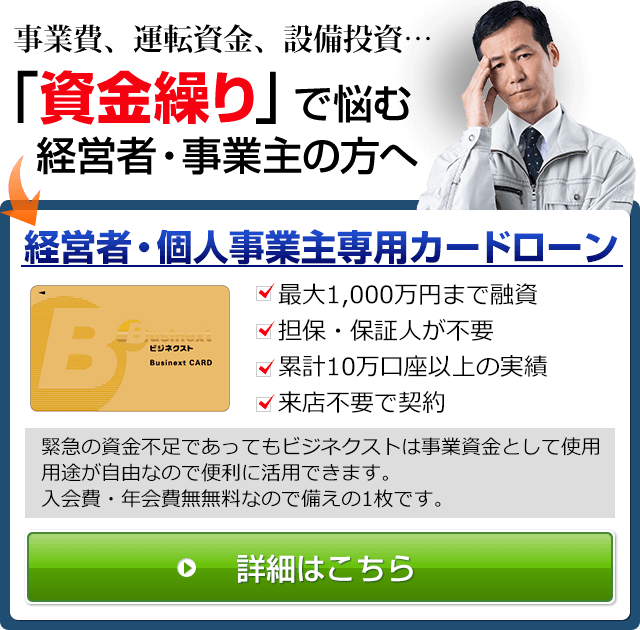個人事業主と会社員の違いを独立前に認識

会社員と個人事業主は収入を得るため仕事をしているという点では同じですが、税金や確定申告など違う点のほうが多くあります。
会社員から独立して個人事業主を目指す、あるいはサラリーマンをしながら副業として個人事業主になるという場合はその違いをよく理解しておく必要があります。
今回は会社員と個人事業主の違いや兼業の場合の注意点などを解説しましょう。
個人事業主にかかる税金
個人事業主になると税金は自分で支払うことになります。
会社員の場合は給与から差し引かれているので意識することはなかった税金ですが、個人事業主になると税金を普段から意識する必要があります。
まずはどのような税金があるのか解説しましょう。
所得税

会社員でも所得税は収めていますが、給与から自動的に差し引かれていて、年末調整で保険料や医療費などを調整する程度なのでいくら税金を支払っているのかわからない人も多いでしょう。
税率に関しては個人事業主も会社員も変わりありませんが、課税の対象となる課税所得に違いがあります。
会社員はほとんど経費が認められていませんが、個人事業主は事業に関する経費が数多くあります。
個人事業主は会社員と違って普段から経費を意識することで、課税対象の金額を減らすことができます。
つまり認められている経費をうまく活用することで、支払う税金を減らすことができるのです。
売上から経費を差し引いた課税所得額に応じて基本控除額と税率が下記のように割り当てられています。
これは会社員でも同じなので源泉徴収票などで確認してみましょう。
| 課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円を超え330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円を超え695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円を超え900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円を超え1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
住民税
住民税も給与所得者、個人事業主に関係なく支払うべき地方税です。
市・県民税(特別区民税・都民税)という名称どおり市と県の2ヶ所に支払います。
会社員の場合は市町村役場に給与支払報告書を送ることで住民税が計算されますが、個人事業主は所得申告の際に自分で記入します。
決定通知書と納付書は企業宛と個人宛の違いはありますが、どちらの場合も4月から5月には市町村が送付します。
会社員は給与天引き(特別徴収)、個人事業主は一括か年4回に分けて支払います(普通徴収)。
住民税の計算は個人事業主であっても自分でする必要はありません。

住民税は均等割と所得割に分けられていますが、東京都の場合は均等割5,000円、都民税4%、特別区民税が6%です。この均等割と所得割の比率は地方自治体で決めることができるので全国一律ではありません。
個人事業税
個人事業を始めたときは最寄りの税務署に開業届を提出する必要がありますが、この届出に基づいて個人事業税を課税するかどうかが決まります。
個人事業税は個人事業主だけが対象となる地方税ですが、すべての事業主が対象となるわけではありません。法律で定められた70業種が対象となります。
これは地方によって解釈の違いがあるので税務署に確認しておく必要があります。
特にアフィリエイターやネット上で仕事をしている場合は、解釈がまちまちなので税務署に確かめましょう。
しかし、事業税には290万円の控除金額があるので、小規模の個人事業であれば税金はかかりません。
税率は業種によって異なりますが3%~5%となっています。
消費税

これも個人事業主だけの税金となります。ただし消費税を支払わなくても良い免税業者もあります。
基本的に消費税は消費者が納税義務者ですが、実際に税務署の消費税を納めるのは事業者となります。
小売業あれば商品売却時に消費税を預かりますが、商品の仕入れの際には逆に消費税を支払っています。
預かった消費税から支払った消費税を差し引いた差額を税務署に納めることになります。
基本的に消費税を納める義務が生じるのは課税対象となる売上1,000万円以上かどうかが基準となります。
具体的には2年前の売上が1,000万円以上、または前年度の特定期間(1/1~6/30)で1,000万円以上になると消費税を納める義務があります。
個人事業主は確定申告が必須
会社員と個人事業主の最も大きな違いは確定申告を行うことでしょう。
サラリーマンでも高額所得者になると確定申告が必要ですが、一般的には年末調整だけで終わる人がほとんどでしょう。
所得税確定申告によって支払う税金が決定するので、個人事業主にとって確定申告書の作成は大事な作業となります。
白色申告
個人事業主は毎年1/1~12/31までの売上に基づいて翌年の3/15までに所得申告をします。
青色申告承認申請書を提出していない場合は、白色申告の扱いになります。
■白色申告で認められている控除
- 基礎控除38万円
- 事業専従者控除:配偶者最大86万円、その他家族一人につき最大50万円
- 10万円未満の資産購入は一括で経費計上できる
白色申告ではそれほど経費は認められていませんが、青色申告に比べて申請にかかる手間が少なく手続きが楽というメリットがあります。
小規模の個人事業であれば白色申告でも問題はありません。
青色申告
青色申告のメリットは控除が多いという点ですが、逆に白色申告に比べて格段に申告手続きが面倒というデメリットがあります。
■青色申告で認められている控除・経費
- 基礎控除38万円(白色申告と同じ)
- 事業専従者給与:配偶者や家族への給与は全額経費となる
- 青色申告特別控除:複式簿記の場合65万円、簡易簿記の場合10万円の控除
- 赤字を3年間繰り越すことができる
- 30万円未満の資産購入は一括で経費計上できる

サラリーマンの場合は経費がほとんど認められていないので、自営業者と比べると不公平感があります。
そのため給与所得者控除(最大65万円)が認められています。
しかし、青色申告では65万円の控除の他に各種控除や経費が認められているので、サラリーマンに比べて所得税に関しては恵まれています。
社会保険料などの控除はサラリーマンと同じ
サラリーマンが年末調整で行うように各種保険や医療費などの控除は個人事業主であっても確定申告時に行うことができます。
■主な控除
- 社会保険料控除:国民年金保険料、国民健康保険料等
- 生命保険料、地震保険料、損害保険料、介護保険料
青色と白色申告のどちらを選ぶか
初めて申告をするときは白色申告のほうが簡単です。会社員から個人事業主になったばかりであれば、そもそも帳簿付けから覚えなくてはいけません。
いきなり正規の簿記はもちろん、簡易簿記もなれていないのに青色申告はハードルが高いでしょう。
もちろん簿記を習ったことがある場合は、むしろ最初から青色申告でも構いません。控除金額が大きく違ってきます。
青色申告にするか白色申告にするかは、事業規模と自分の簿記能力を考慮して決めましょう。
いずれにしても最終的には青色申告を目指すことをおすすめします。
会社員の副業と退職後の独立の注意点
脱サラをして独立をする、副業サラリーマンとして個人事業を兼業する場合、注意する点があるので解説しましょう。
失業保険をもらうなら開業届の時期を考えよう

会社員をやめて個人事業主になる場合の注意点としては失業保険(雇用保険)をどうするかという問題があります。
雇用保険の給付金をもらうつもりがないのであれば何も問題ありません。
しかし、せっかく雇用保険料を支払ってきたのだから、給付金をもらうという人は雇用保険を履き違えています。
雇用保険の給付金は再就職の意志がある人だけが申請できます。
最初から個人事業をするつもりであれば給付金を受け取る資格がないというのが建前です。
しかし、当初は再就職か独立か決めかねているというのであれば、開業届の提出は見送りましょう。
開業届を出してしまうと再就職の意志がないということがハッキリするので給付金は受け取れません。
個人事業開始のめどが充分立ってから開業届をしましょう。
副業禁止の企業で個人事業兼業の場合は住民税に注意

会社の就業規則で副業を禁止している場合、マイナンバー登録で副業が会社に発覚するといった情報がありますが、マイナンバー以前に確定申告でバレる危険性があります。
本来就業規則で禁止されていることをやっている時点で問題ですが、すでにやってしまっている場合は懲戒免職だけは避けなくてはいけません。
確定申告では住民税の支払方法に特別徴収と普通徴収が選択できます。
特別徴収を選んでしまうと給料天引きになるので、会社以外に収入があったことが簡単にバレてしまいます。
確定申告時は必ず普通徴収を選びましょう。
マイナンバーがどのように運用されていくのかわかりませんが、将来はマイナンバーが原因で副業が発覚する可能性もあります。
副業が順調であれば、独立するというのも選択肢の一つです。
開業に必要なもの
個人事業を始めるために最も必要なものは資金です。低金利の公的機関や銀行は審査に時間がかかります。
万が一のために金融機関よりは金利が高くなりますが、在職中にカードローンを作っておくのも一つの方法です。
退職してからでは実績のない自営業者ではカードローンも作りにくくなります。
無金利の期間があるプロミスやSMBCモビットといったカードローンを何枚か作っておきましょう。
利用する優先順位は金利が低い融資からというのが鉄則なので、結局は使わない可能性もありますが全く何もない不安を解消できます。
まとめ
個人事業を新たに始めるというのは簡単なことではありません。事前にしっかりと準備をしておく必要があります。
サラリーマン時代には考えたこともないような税金や確定申告、毎日のように経費のことも考えなくてはいけません。
それも事業の運営を考えながらやらなければいけないのです。
しかしそれでも事業がうまくいったときの喜びはサラリーマンでは得られないものになるでしょう。
今回紹介したことを参考にして独立前にしっかりと準備をしましょう。