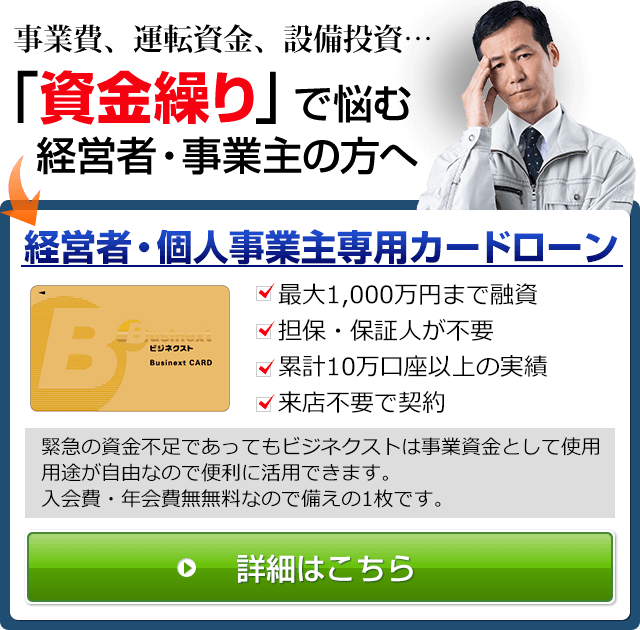ファクタリングの仕訳と会計処理の方法

売掛債権の多い企業にとってファクタリングは売掛債権をすぐに現金化できるので、資金調達方法として利用価値が高い方法です。
しかし、ファクタリングを利用した場合の仕訳処理について不安を感じている担当者もいるのではないでしょうか。
ファクタリングの会計処理自体はそれほど難しいものではありません。
それ以上にファクタリングにはメリットが多いので積極的に活用しましょう。
今回はファクタリングの会計処理方法について解説します。
ファクタリングの基礎
まずはファクタリングの会計処理方法を解説する前にファクタリングの基礎をおさらいしておきましょう。
ファクタリングは売掛債権の譲渡

ファクタリングの対象となるのは売掛債権です。
売上を計上する場合、売上金の支払いが現金・小切手・受取手形・売掛債権のどれかによって勘定科目が異なります。
売掛債権は取引先との取り決めによって締め日・支払日を決め、それに従った一定期間の売上高をまとめて支払う金銭債権の一種です。
つまり売掛金は支払いを猶予した「ツケ」と考えることができます。
飲食店でのツケと違うのは、支払う期日が決められているという点です。
ファクタリングはこの売掛債権を第三者のファクタリング業者に譲渡することで、現金化する方法です。
ファクタリングの種類
ファクタリングの種類はいくつかありますが、最も一般的なのは「一括回収ファクタリング」で、一般企業が売掛債権の現金化に利用しています。
その他にも保証ファクタリングや医療報酬債権ファクタリング、国際ファクタリングがあります。
今回は一括回収ファクタリングの仕分けに関して解説します。
一括回収ファクタリングはさらに2種類のファクタリングに分類できます。
・2社間ファクタリング
・3社間ファクタリング
ファクタリングでは売掛債権を売却する会社、売掛債権先企業、売掛債権を買い取る業者の3社が関係します。
売掛債権先に譲渡の事実を知らせるかどうかで2社間・3社間ファクタリングに分けられます。
2社間ファクタリングは売掛先に譲渡の連絡をしないため、取引先に知られずに譲渡ができますが、業者のリスク対策のため手数料が高くなります。
売掛債権譲渡人とファクタリング会社の2社間取引となります。
3社間ファクタリングは売掛先に譲渡の連絡をするため業者のリスクが少なく手数料は安くなりますが、取引先との関係に支障が出ることがあります。
2社間ファクタリングの当事者に加えて売掛債権先企業も当事者となります。
ファクタリングの仕訳
売掛金が発生してからファクタリングによる現金化までの仕訳を順追って解説しましょう。
売掛金による売上の発生時
売上は収益ですが、現金ではなく売掛金となった場合は支払いを約束した債権なので資産になります。
売掛金が発生した場合は下記のように会計処理します。
借方 |
貸方 |
|---|---|
売掛金 100万円 |
売上 100万円 |
ちなみにファクタリングを利用せずに、売掛金の支払いを取引先から受けた場合は下記のように処理します。
借方 |
貸方 |
|---|---|
現金 100万円 |
売掛金 100万円 |
売掛金の支払いは取引先との取り決めによりますが、数ヶ月ほどかかることもあります。
その間は現金が入金にならないので、仕入の支払いなどに利用することができません。
そこでファクタリングを利用して早期に現金化することが有効となります。
ファクタリング利用時の会計処理
ファクタリングの契約が成立してもすぐに入金となるわけではないので、ファクタリング契約時と入金時に分けて仕訳をします。
ファクタリング契約時
借方 |
貸方 |
|---|---|
未収金 100万円 |
売掛金 100万円 |
ファクタリング契約時にはまだ現金化されていないので、振り込まれるまでは借方科目を未収金、貸方科目を売掛金として処理します。
ファクタリング会社からの入金時
借方 |
貸方 |
|---|---|
普通預金 90万円 |
未収金 100万円 |
ファクタリング会社からは手数料を差し引かれて振り込まれるので、手数料については「売掛債権譲渡損」として計上します。
また売掛債権譲渡損ではなく「支払手数料」「雑損失」「債権割引料」などで処理することも可能なので、自社で普段使っている勘定科目や会計ソフトの勘定科目に合わせて対応しましょう。
振込先が当座預金であれば勘定科目は当座預金にします。
債権譲渡登記にかかる費用の仕訳
2社間ファクタリングではファクタリング会社のリスク軽減のために、「債権譲渡登記」を行なうのが一般的です。
3社間ファクタリングの場合は、売掛先企業から直接ファクタリング会社に売掛金が支払われるので、リスクが少ないので登記は必須ではありません。
登記費用は司法書士への報酬と印紙代や登録免許税の実費に分けられます。
借方 |
貸方 |
|---|---|
支払報酬 15万円 |
現金 20万円 |
司法書士の報酬は「支払報酬」、印紙代・登録免許性については「租税公課」の借方科目を使用します。
ファクタリングでオフバランス化
オフバランスのバランスはバランスシート(貸借対照表)からオフする、つまり貸借対照表に記載しないという意味です。
ファクタリングを利用することでオフバランスができますが、オフバランスにはどんな効果や意味があるでしょうか?
資産のオフバランス

資金調達方法にはファクタリングの他に銀行融資などもありますが、貸借対照表には負債として記載されます。
また売掛金のままで入金を待っている状態でも貸借対照表には売掛金と記載されます。
ファクタリングを利用した場合は現金化ができるので、現金として記載され負債や売掛金の扱いにはなりません。
つまり本来資産として計上しなければいけないものが、現金化によって資産の部から外すことができます。
これが資産のオフバランスです。
総資産額が減少することによって、財務指標であるROAや自己資金比率が上昇します。
ROAや自己資金比率への影響
自己資本比率は「自己資本÷総資本」で計算され、比率が高いほどその企業の安全性が高いと評価されます。
ROEは「当期純利益÷自己資本」で計算され、比率が高いほど少ない資本で高い利益をあげていることになり企業の評価も高くなります。
ファクタリングを利用することでどちらの比率も高くなり、融資を利用したときよりも同じ利益にも関わらず財務指標が改善されます。
こうした点がファクタリングのメリットのひとつですが、反対に手数料がかかるため経費が増加するという点はデメリットになります。
特に2社間ファクタリングについては登記費用などの負担もあるのでデメリットが大きくなります。
ROAと自己資金比率改善のメリット

ファクタリングでROAと自己資金比率改善ができることがわかりましたが、それによって具体的にはどんなメリットがあるでしょうか?
自己資金比率が高いと企業として安定性が高くなるので、銀行融資の審査で有利になります。
銀行は安定性の高い企業の融資をするので、ファクタリングの利用は銀行の評価を高めることにつながります。
ROAの比率が高いと、特に投資家の評価が高くなり間接的に株価の上昇につながります。
売掛金の多い企業はファクタリングを活用することで、財務指標の改善になり企業としての評価を高めることになります。
ファクタリング以外の資金調達方法
ファクタリングでは売上債権売却により資金を調達し、なおかつ財務指標の改善にも役立ちます。
同じような効果がある資金調達方法を利用すればさらにメリットが大きくなります。
売掛債権以外に手形取引によって受取手形も多い場合には、手形債権も現金化することでファクタリングと同じ効果が得られます。
手形割引は銀行や専門業者に持ち込みすれば、支払期日前に現金化することが可能です。
手形の割引処理にも手数料がかかりますが、現金化のメリットを考えると手数料を支払う価値はあります。
受取手形やファクタリングはROAや自己資本比率の改善に役立つと解説しましたが、もうひとつキャッシュフローの改善もできます。
キャッシュフロー計算書も銀行融資ではチェックの対象で、プラスになるほど会社の評価も高くなるので、ファクタリングとともに手形割引も活用しましょう。
まとめ
ファクタリングの会計処理については理解いただけたでしょうか?
ファクタリングの会計処理から財務指標の改善になることも理解いただけたことと思います。
ファクタリングや手形割引を利用し、現金化することで、銀行評価も高くなり融資審査に有利になります。
融資を受けないことで融資審査に有利にするというのは矛盾しているようですが、資金繰りの手段は多様なほどあらゆる場面に対応できます。
銀行融資ばかりに頼り切っていると、財務指標が悪化してれ融資審査で断られることにもなりかねません。
特に中小企業経営者は銀行融資を確保するためにも、偏った資金調達方法は避けて、様々な方法で資金を調達しましょう。