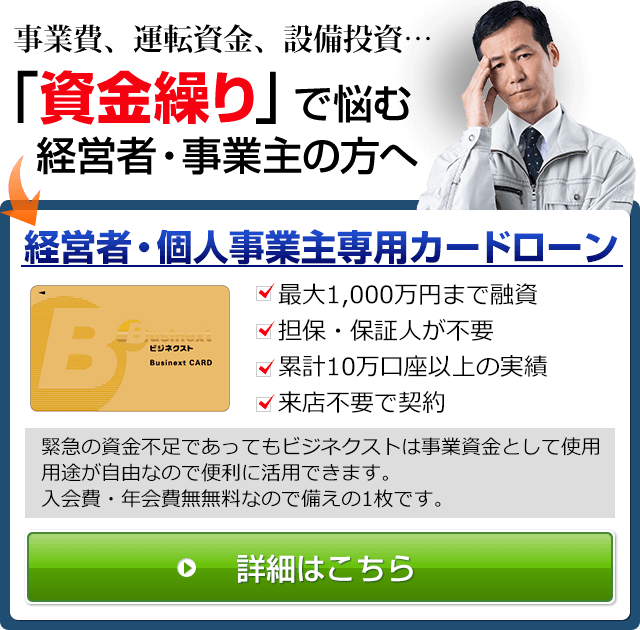生産性向上設備投資促進税制とは?

中小企業経営者は経費節減や節税について知識を深めることも重要です。
特に税金に関しては優遇税制や節税方法は税務署が積極的に教えてくれるわけではありません。
税金を申告しなければ強制的に取り立てられますが、税金が戻ることに関しては自分から申告しなければ戻らない仕組みになっています。
経済産業省管轄の産業競争力強化法に基づく「生産性向上設備投資促進税制」もそのひとつです。
知識不足で損をしないように生産性向上設備投資促進税制についての知識も深めましょう。
生産性向上設備投資促進税制の概要
生産性向上設備投資促進税制を簡単に説明すると、対象となる設備投資をした場合に税額控除ができる制度です。
実は一部は終了していますが、まだ税額控除は利用できます。
その点も含めて概要について解説しましょう。
概要と対象者

生産性を高める設備投資を行なった場合に、即時償却や最大5%の税額控除ができるのが、生産性向上設備投資促進税制です。
対象となるのは青色申告をしている中小企業や個人事業主となります。
特に業種が限定されているわけではないので青色申告者であればだれでも対象となるのがメリットです。
優遇措置は下記の適用期間に実施され終了しましたが、一部の設備は優遇措置を受けることがまだ可能なので後述します。
▼平成26年1月20日~平成28年3月31日
上記期間中に対象設備を取得・事業の用に供した場合、取得価額の5%税額控除(建物及び構築物は3%)又は即時償却
▼平成28年4月1日~平成29年3月31日
上記期間中に対象設備を取得・事業の用に供した場合、取得価額の4%税額控除(建物及び構築物は2%)又は特別償却50%(建物及び構築物は25%)
適用対象資産(設備)
優遇税制の対象となる設備は生産性向上が認められる下記の2種類の設備に対する投資となります。
A)先端設備(A類型)
対象機器は最新モデルで生産向上性が1%以上の設備が対象となりますが、設備の購入者には対象となるか判断できません。
そのため設備メーカーに証明書発行を依頼し工業会などから確認してもらう必要があります。
反対に考えると証明書があれば節税できるので、次に説明するB類型設備に比べて簡単に利用できます。
B)生産ラインやオペレーションの改善に資する設備(B類型)
Aと違い最新モデルという条件もないので幅広い設備が対象となりますが、利益計画書を経済産業局に提出して設備導入による利益増加を説明する必要があります。
1.利益計画の策定
2.公認会計士、または税理士の確認書を取得
3.経済産業局へ書類を提出
4.経済産業局から確認書を取得
B類型は上記の事前手続きが必要ですが、A、Bともにさらに価格と適用となる設備の要件をクリアする必要があります。
取得価額要件と具体的な対象設備
A、Bともに下記の価格条件をクリアする必要があります。
| 機械装置 | 単品160万円以上 |
|---|---|
| 工具・器具部品 | 単品120万円以上または単品30万円以上で事業年度内合計120万円以上 |
| 建物 | 1単位120万円以上 |
| 建物付属設備 | 1単位120万円以上または1単位60万円以上で事業年度内合計120万円以上 |
| 構築物 | 1単位120万円以上 |
| ソフトウェア | 1単位70万円以上または1単位30万円以上で事業年度内合計70万円以上 |
上記は設備単位で判断するので設備の種類が違っていても単位が同じであれば、事業年度内で合計することができます。
また、A、Bともに適用対象設備や対象外の設備があるので事前に確認しておきましょう。
参考資料:生産性向上設備投資促進税制について(経産省)
B類型はすでに終了、A類型はまだ間にあう
残念ながらB類型に関してはすでに優遇税制が終了しています。
しかしA類型については平成29年3月31日までに取得して事業に使用していれば、次の確定申告までに証明書を取得すれば控除の対象になります。
A類型の申請方法など注意点を解説しましょう。
申請と必要書類

B類型がすでに終了しているのは利益計画を事前に提出する必要があるからです。
A類型の場合、必要なのは設備の性能を証明する書類だけで、証明書は設備取得後でも取得できるのでまだ対象となります。
基本的には確定申告書に工業会発行の証明書を添付して、控除を申請することで対象となる控除を受けることができます。
B類型と比べると事前に提出する書類もないので、対象金額と対象設備かどうかをチェックしておけば申請自体は難しいことはありません。
手引き書をよく読んでから申告しましょう。
証明書発行手続きについては、設備メーカーが証明書とチェックシートを記入し担当の工業会(日本工作機械工業会など)の確認を受ける流れとなります。
詳しくは経済産業省ホームページで確認しましょう。
補助金などをすでに受けている場合
設備投資のときに利用できる補助金・助成金などがありますが、すでにそうした補助金を受けている場合は控除を受けられるでしょうか?
結論としては控除を受けることができますが、取得価格は補助金などを除いた金額となります。
単品で160万円以上の条件となっている機械装置の場合、補助金を差し引いて160万円以上なければ控除の対象にならないので注意しましょう。
対象外の設備
適用要件を満たす設備でも用途や状態によっては対象外となるので、しっかり確認してから申請しましょう。
・対象外の設備
・中古資産
・貸付資産
・海外で使用する設備
・本店・寄宿舎等、事務用品器具備品、福利厚生施設等の生産性に寄与しない設備
リースを利用した場合の扱い
設備の導入ではリースを利用することが多いですが、購入ではなくリース利用の場合は対象となるでしょうか?
リースにもいくつか種類があるので、リースの種類によって取扱が違うので注意しましょう。
▼オペレーティング・リース
オペレーティング・リースは完全に賃借で、リース利用者には所有権はありません。
つまり資産にはならないので設備の取得価格が控除の対象となる生産性向上設備投資促進税制の対象外となります。
▼ファイナンスリース
基本的にファイナンスリースは実質的にお金を借りて購入するのと同じなので対象となります。
しかしファイナンスリースにも2種類あり、その種類によって多少違いがあります。
| 所有権移転ファイナンスリース取引 | 税額控除または即時償却、特別償却からの選択 |
|---|---|
| 所有権移転外ファイナンスリース取引 | 税額控除のみ利用可能 |
なお、リースを利用している場合はリース料ではなくリース資産額が控除の計算対象となるので注意しましょう。
生産性向上設備投資促進税制のメリット
それでは具体的に生産性向上設備投資促進税制にはどんなメリットがあるのかをご紹介しましょう。
最大4%の控除
取得価額の4%(建物・建築物は2%)の税額控除となります。
法人課税対象額2,000万円、設備投資金額1,000万円の場合次のように節税できます。
| 本来の法人税額 | 2,000万円×40%=800万円 |
|---|---|
| 4%を控除した場合 |
1,000万円×4%=40万円 800万円-40万円=760万円(控除後の納税額) |
ただし本来の納税額の20%が税額控除限度額なので、最大でも160万円の控除となります。
特別償却最大50%

4%の控除以外に、50%の即時償却を選択することができます。
1,000万円の設備投資であれば、初年度に500万円を一括で償却することができます。
しかし、対象設備が5年の耐用年数であれば、5年かけて減価償却するのと半額を一括で償却して残りを4年で償却するのもトータルでは変わりはありません。
つまり控除される税金は5年のトータルでは同じということになります。
一括で償却をするときは、その事業年度だけ償却金額を増やしたい場合にだけ意味があります。
売上が急増して利益が大きいときに一括償却をすることで、納税金額をおさえることができるからです。
つまりタイミングが重要なので、特に特例適用事業年度が他の年度と事情が変わらないのであれば4%の控除を利用したほうのメリットがあります。
控除と償却の選択

生産性向上設備投資促進税制を利用しなくても、設備投資をして固定資産を取得すれば減価償却をすることができます。
ただし、定率法を利用すれば初年度にある程度高額な償却もすることができます。
金額的には50%の一括償却をしたほうが4%の控除を受けるよりもメリットがあるように思えます。
しかし、4%控除を受けても減価償却をすることができるので、金額は少なくなりますが純粋に節税につながります。
一方で減価償却費を大きくするメリットは、通常よりも大きな利益となった場合に、高額な減価償却費によって税金を控除できるという点です。
設備投資が期初に近く、期中にその効果によって売上が増大したときなどは、50%の特別償却は効果があるでしょう。
反対に期末近くの設備投資で売上にまだ反映されていない場合は、4%の控除のほうが効果は大きい可能性があります。
どちらを選択するかは自社の決算事情により決めましょう。
まとめ
中小企業に対する税法上の優遇措置はいろいろありますが、中小企業経営者はこれらの情報を積極的に収集して活用しましょう。
今回ご紹介した「生産性向上設備投資促進税制」のように、すでに適用期間自体は終了しているものもあります。
こうした優遇税制は期間限定のケースが多いので、タイミングを逃さないようにしましょう。