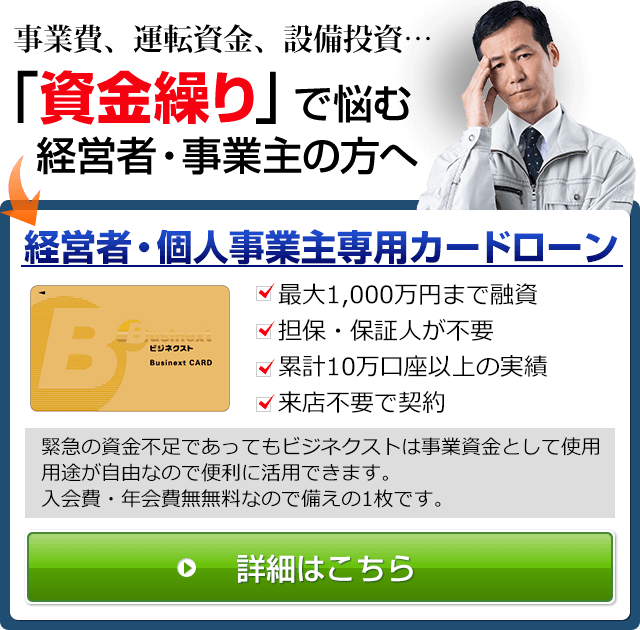地方自治体が取り組む制度融資とは

中小企業者にとって事業資金調達方法としては融資が一般的です。
その中でも低金利の公的融資を活用している経営者は多いのではないでしょうか。
公的融資の代表としては日本政策金融公庫がありますが、もうひとつ地方自治体の制度融資があります。
制度融資は市区町村単位で利用できるという点で、日本政策金融公庫の窓口よりも利用しやすいという利点があります。
今回は制度融資とは何か、どのような利用に向いているのか、利用の流れなどを解説しましょう。
制度融資の仕組み
制度融資の仕組みは同じ公的融資の日本政策金融公庫と比べてどのような違いがあるでしょうか?
信用保証協会とセット

制度融資は都道府県や市区町村などの地方自治体が主導する融資制度です。
しかし、制度融資では実際に融資を実行するのは地方自治体ではなく金融機関となります。
この点は直接融資実行をする日本政策金融公庫と大きく違っています。
融資を実行するのは取扱金融機関で、必ず信用保証協会付き融資となっている点も、信用保証協会が利用できない日本政策金融公庫と異なる点です。
地方自治体は信用保証協会に保証料の補填や損失補てんを行ない、企業側に融資のあっせんをするだけで直接融資には関わらないのです。
また信用保証協会がセットとなっていることで、連帯保証人は基本的に代表者だけですむので、融資を受けやすい要素となっています。
制度融資の仕組みは自治体によって違う
制度融資を受けるための要件は地方自治体によって違うので、自社の主たる事務所がある自治体の制度を事前に調べておくことが大切になります。
制度融資は基本的に事務所所在地以外で融資を受けることはできないからです。
しかし制度融資に共通する要件があるので、まずはそれを確認しましょう。
- 中小企業者であること
- 融資を受ける地方自治体の地域内で一定期間事業を営んでいること
- 税金を納付していること(延滞がないこと)
- 過去に融資を受けたり、保証人になったりしている場合には、その返済に延滞等がないこと
- 許認可が必要な業種を営んでいる(営む)場合には、その許認可を受けている(受ける)こと
融資の審査は金融機関と信用保証協会が行なう

地方自治体があっせんする以外は、民間金融機関の信用保証協会保証付き融資と流れはほとんど変わりません。
日本政策金融公庫は信用保証協会が利用できませんが、そのため単独で審査を行なうので融資実行までの期間は短くなります。
制度融資は融資実行をする金融機関と信用保証協会が審査をするので時間がかかります。
責任共有制度ができてからは、特に金融機関の審査も慎重になっています。
責任共有制度は信用保証協会が信用保証額の80%、金融機関が20%の負担割合となる制度です。
以前は100%信用保証協会が保証していたので、銀行などの金融機関は審査といっても条件をクリアするかどうかのチェック程度でした。
しかし、20%とはいえ銀行にもリスクがあるので、審査は以前に比べると厳しくなっているのは事実です。
金利と信用保証料
制度融資では金利の他に信用保証協会に信用保証料を支払うことになります。
金利に上乗せになるので負担は大きくなりますが、もともと低金利の上に保証料を地方自治体が一部補助することもあります。
そのため金融機関から直接借り入れするプロパー融資よりは低金利で利用できます。
自社の該当する自治体の制度融資がどの程度の金利・保証料で貸付しているのかは事前に調べておきましょう。
申し込みの流れ
申込みの流れも自治体によって違いますが、一般的な流れをご紹介しましょう。
- 地方自治体の窓口で申し込みをし、金融機関への紹介状をもらう。
- 必要書類とともに金融機関に申し込みをする。
- 金融機関を通して、信用保証協会への申し込みが行なわれる。
- 信用保証協会で審査をする場合、面談が必要な場合がある。
- 信用保証協会の審査を通過すると金融機関の審査をする(金融機関が先に審査することもある)。
- すべての審査が終了すると融資実行が実施される。
※中小企業診断士による簡単な審査がある場合もある。
自治体によって多少の違いはあっても大まかな流れとしては上記のとおりとなります。
必要書類
参考として東京都の制度融資で必要な書類をご紹介しましょう。
基本的には他の都道府県も大きな違いはありません。
- 信用保証委託申込書
- 信用保証委託契約書
- 個人情報の取扱いに関する同意書
- 印鑑証明書(申込人及び連帯保証人のもの)
- 確定申告書(決算書)の写し(原則直近2期分)
- 納税証明書(法人税<その1>または事業税
- 見積書または契約書の写し(設備資金の場合のみ)
- 創業計画書(創業融資を利用する場合および業歴1年未満の場合)
- 商業登記簿謄本(法人の場合のみ)
上記以外に制度融資によって必要な書類の提出もあるので確認しておきましょう。
また、銀行の審査では事業計画書や資金繰り表、キャッシュフロー計算書があると審査がスムーズになるので準備しておきましょう。
制度融資のメリット・デメリット
制度融資にはどんなメリットやデメリットがあるのでしょうか?
次は制度融資利用によるメリットとデメリットを解説しましょう。
制度融資のメリット
制度融資は中小企業や小規模事業者を都道府県や市区町村といった地方自治体が支援する制度です。
お金が借りやすいように低金利で保証料の援助なども行ない、保証人無しで事業資金や創業資金の調達を援助しています。
そのため下記のメリットがあります。
・一定の要件を満たせば個人事業主も利用できる
・利子や保証料の補助を受けられるケースが多い
・低金利で固定金利なので長期返済ができる
・据置期間も最長1年のケースがある
・創業資金や倒産対策資金にも対応
・法人は代表者の連帯保証だけで、第三者保証人不要
基本的に小規模事業者への援助目的なので、民間金融機関の融資ではできない企業再生や倒産防止などの利用もできるメリットもあります。
制度融資のデメリット

制度融資最大のデメリットは申込みから融資実行まで2ヶ月程度かかるという点でしょう。
地方自治体・金融機関・信用保証協会それぞれが受付手続きと審査をして、さらにお互いに書類のやり取りもするので必然的に時間がかかります。
そのため緊急を要する事業資金調達には向いていません。
また日本政策金融公庫では自己資金要件は10%ですが、制度融資の場合は自己資金比率50%を求めることが多いのもデメリットです。
つまり自己資金の金額と同額までしか借り入れできないということです。
制度融資の種類にもよりますが、基本的には自己資金の不足を調達する使い方がいいでしょう。
日本政策金融公庫との比較
同じ公的金融機関には日本政策金融公庫があります。
日本政策金融公庫と制度融資を比較することで、よりメリットやデメリットが明確になります。
|
制度融資 |
日本政策金融公庫 |
|---|---|---|
金利 |
低金利 |
低金利 |
保証料 |
あり |
なし |
窓口 |
都道府県 |
日本政策金融公庫の窓口のみ |
融資実行までの期間 |
約2ヶ月 |
1ヶ月以内 |
自己資金比率 |
50% |
10% |
融資実行 |
民間金融機関 |
日本政策金融公庫 |
関連機関 |
地方自治体 |
日本政策金融公庫 |
担保 |
不要 |
不要 |
連帯保証人 |
法人代表者 |
法人代表者 |
上記の表を見ると基本的には、自己資金比率や融資実行期間以外はどちらも大きな違いはないように思えます。
どちらを利用するのかは、自社が融資提供要件に合致するのかどうか、自己資金がどれくらいあるのかで決めるといいでしょう。
また、制度融資では利息補助がメリットのひとつなので、利息補助で返済を軽減したい場合は制度融資を検討しましょう。
どちらも融資実行期間は短いとはいえないので、緊急に必要な事業資金には向かないという点では共通しています。
また公的機関の融資は民業圧迫という観点から、民間金融機関融資の借換には利用できないので注意しましょう。
まとめ
公的融資は設備投資などでお金がかかる創業融資で利用すると効果的です。
低金利で長期返済も可能なので起業時の負担を軽減することができるので、起業家は最初に検討すべきです。
制度融資は地方自治体の利子補給や保証料補助を受けられることが多いので、特にメリットが大きい融資制度です。
自己資金に余裕があれば制度融資、あまり余裕がなければ日本政策金融公庫を選びましょう。
中小企業経営者は資金調達の手段を数多く持っていると、スムーズな経営ができます。
制度融資もそのひとつに加えましょう。