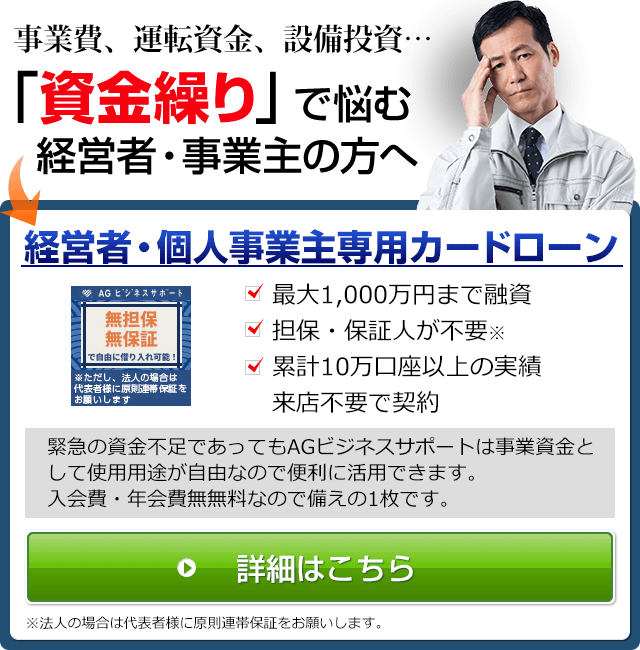法人名義でマイカーローンは利用できる?社用車を持つ方法を解説
ほとんどの法人では社用車や営業車が不可欠で、中には車両がなければ事業が成り立たない業種もあります。
そのため車両購入は不可欠という法人が多いのですが、車両の購入にはいろいろな方法があり、それぞれメリットやデメリットがあります。
今回は車両の購入方法について検証してみましょう。
車両購入に必要な費用
 車両を1台購入するためには、車両の価格以外に税金や保険など様々な諸費用の支払いが発生します。
車両を1台購入するためには、車両の価格以外に税金や保険など様々な諸費用の支払いが発生します。
ここで紹介する諸費用は車両を購入したときに必ず支払うことになりますが、車種や排気量によって大きく変わってくるので比較したいポイントです。
では、車両購入に関する費用にはなにがあるかをチェックします。
自動車本体の価格は自動車ディーラーに支払うものですが、それ以外に税金や保険料の支払いをしなければ車両を購入することはできません。
新車の購入にかかる諸費用には以下のものがあります。
排気量によって決められる都道府県税で、1,501cc~2,000ccの場合年額39,500円だが、購入時は購入月によって税額に違いがある。
3月購入では課税はなく4月購入は39,500円となる。
必ず課税される都道府県税で、取得価格の5%(軽自動車は3%)
毎年発生する国税だが、購入時と車検時にまとめて支払う。
1.5t~2.0tで1年分25,200円。
自動車の所有者か使用者が必ず加入しなければいけない保険。
車検時に一括払いし、平成29年度では36ヶ月分で35,950円。
1台あたり6,000円から18,000円程度で、エアバッグなどのリサイクル料金を購入時に支払う。最終的に廃車する人が支払うので、自動車を譲渡した場合リサイクル料金は戻ってくる。
これ以外にも販売店などに支払う費用があります。
消費税、登録費用、車庫証明費用、納車費用、下取費用など。しかし、登録や車庫証明、納車費用は自分で手続きしたり、車両を引き取りに行ったりすれば不要な費用です。
諸費用の支払い方法
 車両本体と消費税に関しては、現金でもクレジット会社の立て替え払いによるローンでも購入できますが、車両購入時に必要な諸費用に関しては現金払いが原則です。
車両本体と消費税に関しては、現金でもクレジット会社の立て替え払いによるローンでも購入できますが、車両購入時に必要な諸費用に関しては現金払いが原則です。
車両を引き渡すためには車両の登録が必要になりますが、諸費用のほとんどは登録に必要な費用なので、実費として前払いする必要があるからです。
そのため少なくとも諸費用分は頭金としてローンを組むというのが一般的です。
しかし、現在では諸費用を含めたローンを取り扱うクレジット会社も増えています。銀行ローンでも諸費用込みでのローンは可能な場合がありますが、法人として車両購入するなら、諸費用はほとんど税金なので一括して現金で支払うほうがいいでしょう。
車両本体に関しては固定資産となりますが、諸費用は租税公課や保険料として経費計上できるので、ローンに含めないほうが会計処理もスムーズにできます。
法人の車両維持費
自動車は購入してからも維持費がかかりますが、主な維持費には以下の費用があります。
・ガソリン代
・車検費用(定期点検含む)
・修理費用・消耗品
車両購入時に自賠責保険には加入しますが、それだけでは不足なので任意の自動車保険に加入するのが一般的です。
また、車検は法律で定められているため購入の3年後、それ以降は2年ごとに必ず受けなければなりません。
ガソリン代は定期的にかかる費用で、オイルやウオッシャー液などの消耗品や故障した場合の修理費用もかかります。維持費の一部を前もって予測して組み込むメンテナンスリースもありますが、都度、現金で支払うのが一般的ではないでしょうか。
また、ガソリン代は法人クレジットカードで支払う方法も定着してきました。
法人が車両を購入する方法
法人が車両を購入する場合の支払い方法はいくつかありますが、それぞれのメリットとデメリットについてもあわせて解説します。
車両を現金購入
 現金で車両を購入した場合は、車両本体価格は固定資産として減価償却をすることができ、諸費用に関しては、それぞれ租税公課や保険料として会計処理ができます。
現金で車両を購入した場合は、車両本体価格は固定資産として減価償却をすることができ、諸費用に関しては、それぞれ租税公課や保険料として会計処理ができます。
資金に余裕がある場合や購入台数が1台といった場合には、それほど負担がないので会計処理がシンプルになるというメリットがあります。
しかし購入台数も多くなると、現金払いは負担が大きくなるデメリットがあります。
オートローンもオートリースも基本的に法人で申し込みした場合は、代表者が連帯保証人になるのが原則ですが、個人保証はしたくないのであれば現金払いにするといいでしょう。
車両購入などの高額な固定資産は一括で経費として計上できないため、法定耐用年数に基づいて数年に分けて計上します。これを減価償却と呼んでいます。
減価償却方法には定額方式と定率方式がありますが、税務署に減価償却方法を届け出ていなければ、個人事業主は定額法、法人は定率法によって処理します。
届け出をすればどちらの方法でも処理は可能です。
定額法では毎年同じ金額を減価償却費として処理しますが、定率法は初年度の金額が最も大きく、翌年度以降はしだいに金額が少なくなるという特徴があります。
車両をローンで購入
 車両をローンで購入することは個人だけでなく、法人でも可能です。
車両をローンで購入することは個人だけでなく、法人でも可能です。
ただし車両をローンで購入しても固定資産であることは変わりないので、減価償却の処理が必要となります。
自動車を購入するローンは2種類あります。
ひとつは立て替え払いによる信販会社のローン、もうひとつは融資による銀行ローンです。
どちらを利用しても信販会社のローンは手数料、銀行ローンは借入金額のうち利息が経費として計上できます。
立て替え払いのローンは信販会社だけでなく、メーカー系のクレジット会社もあります。
メーカー系ローンではキャンペーンなどで優遇金利、低金利となることがメリットです。
さらに新車ディーラーが融資をし、その保証会社としてメーカー系クレジット会社が付く場合もあります。
これらは「自動車ローン」「オートローン」「マイカーローン」といった名称が使用されているので、名称だけでは区別がつきません。利用する前にはどういった事業者がおこなっているローンメニューであるかを確認する必要もあります。
ローンは資金に余裕がない場合は、分割で支払えるというメリットがあります。しかし会計上は手数料や利息の仕訳が発生するのため、それがデメリットになります。
車両リースを利用
 リースは簡単に言うと長期のレンタルに近いサービスです。
リースは簡単に言うと長期のレンタルに近いサービスです。
レンタルとの違いはリース利用者の希望商品をリース会社が代わりに購入して賃貸するという点です。
そのためレンタルでは商品の交換ができますが、リースでは商品は交換することができないので注意しましょう。
車両を対象としたリースは法人が利用するのが一般的で、新車だけでなく中古車リースも可能です。
リース車両を購入するのはリース会社なので、利用者にとって車両は固定資産にはなりません。そのため減価償却も不要で、リース料金を経費として計上するだけのシンプルな会計処理になる点がメリットです。
オートリースやカーリースといったサービス名となっていますが、車両のリースにはいくつか種類があります。
・メンテナンスリース
ファイナンスリースはオートローンと同じように、車両価格に諸費用を加えた購入費用をリースします。またファイナンスリースでは残価設定をすることで、月々のリース料を抑えることもできます。
メンテナンスリースはこれらの他に車検費用やオイル、タイヤ交換などの維持費も含めてリースが可能です。
リース車の将来の下取り価格の見積金額を残価として、リース対象から差し引くことでリース料金を抑えることができます。
例えば、3年ごとに営業車を入れ替えるという法人であれば、リース料を低くするメリットがあります。
一方、デメリットとしてリース契約期間内は中途解約ができないため、リース期間中に車両が事故などで使用できなくなった場合でも、多額の解約金が請求されてしまいます。
自家用自動車と違い、営業車両は使用頻度も高く、適切な原価設定が難しくトラブルになることもあります。利用頻度が高いことで事故率も高くなるため、万が一のことを考えると購入したほうが安心できます。
諸費用と維持費の支払い方法
車両を購入する場合、諸費用は先に支払うように要求されることがあるのは、自動車ディーラーが車両登録する際に立て替えて支払うことになるからです。
特に購入台数が多いと費用が膨大となり、ディーラーも立て替えするのが厳しくなるためです。
購入する法人も資金に余裕があれば現金で支払いできますが、そうでなければ法人カードローンを利用するという方法もあります。
ただしカードローンは金利が高いので、売掛金が回収期日や資金調達日までの、短期のつなぎ融資として利用しましょう。
特に車両もローンを利用する場合は、返済が二重になるので法人カードローンのリボ払いは控えましょう。同様に、車両の維持費などを一時的につなぐために法人カードローンを利用することもできます。
どの方法も一長一短あるので、利用するのに一番都合のいい方法を選択するようにしてください。
まとめ
車両の購入方法の中でもローンやリースは与信審査があります。
購入車両台数が多く高額となった場合、ローン審査を通過しない可能性も否めません。
また、借り入れする場合は利息・手数料がかかるので経費計上できるとはいえ負担が大きくなります。ローンを利用して購入する場合はこうした点も考慮して利用しましょう。
車両をそれほど利用しないのであれば無理して購入せず、レンタカーやカーシェアリングを利用する方法もあります。
高額な借入も維持費も必要なくなるので、営業車両が必要のない業種の事業者はこのような方法も検討しましょう。
法人が車両を購入・利用する方法には様々あるので、自社の実情に合わせて適切な方法を選部ことが大切です。